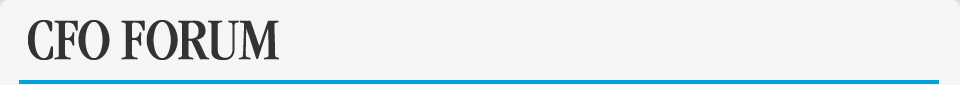
2020年3月16日

グローバル・コミュニケーション
国際コミュニケーション戦略の必要性
─多言語環境と言語対応の類型論から─
本名 信行
青山学院大学名誉教授
一般社団法人グローバル・ビジネスコミュニケーション協会代表理事
猿橋 順子
青山学院大学教授
一般社団法人グローバル・ビジネスコミュニケーション協会理事
はじめに
企業には、ビジョンやミッションがあるが、国際コミュニケーション戦略は、それらを実現するために必要な言語・コミュニケーション関連の対応を担う。およそ言語やコミュニケーションの問題と無縁でいられる企業はあり得ないため、国際コミュニケーション戦略は企業の規模や業種を問わず必要ということになる(CFO FORUM 90号 グローバル・コミュニケーション「国際コミュニケーション戦略とは何か─トップマネジメントの役割─」参照)。
多言語環境と言語対応の類型論
「今後、社会はますます多言語化する」という指摘に対して、「社会は以前から言語的に多様だった。むしろ強い言語(たとえば英語)への収斂傾向がある」という反論も成り立ちうる。これは社会をどの範囲、どの期間で見るか、言語をどう定義するかによっても違ってくるので、一概にどちらが正しいとも言えない。企業ひとつをとってみても、企業内は日本語で均一だったり、部署ごとには言語が統一されていたとしても、取引先や顧客の言語がさまざまであれば多言語環境にあるということになろう。
2020年3月16日






