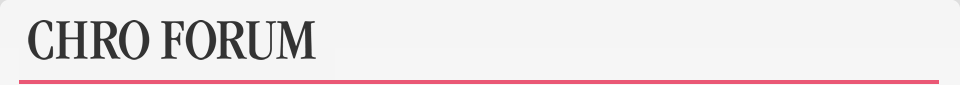
2025年1月10日

人材開発
人事部門は幹部に対し、権力の光と影を伝えることが必要だ ─権力を手放す恐怖と向き合って賞味期限を決めよう─
藤岡 長道
合同会社FJRC 代表社員、日本人材マネジメント協会(JSHRM)元理事長
株式会社J-Labo 主席研究員、CMA 日本証券アナリスト協会会員(職業倫理試験委員)
システム監査技術者、上級システムアドミニストレータ、アクションラーニングコーチ
一度手にした権力を手放すのは難しい
一度手にした権力を手放すのは難しい。それは権限に伴う「影響力を失うことへの恐怖」が大きいからだ。独裁者でなくても、立場による権限には影響力がある。大統領、大臣、会長、社長、事業部長、理事長、委員長、師団長、監督等、その名称は様々だが、その責任は決断、判断であり、その権限には部下への広範な影響力が含まれる。自分が抱いている目的を達成するために、目標に進むために、権限を行使できることは、快の感情をもたらす。したがって、立ちはだかる壁があれば、それを「乗り越えていこう」「壊していこう」という意欲が高まっていく傾向がある。権力者にとっては、権限を行使し影響力を発揮することが、モチベーションのエンジンとなる。したがって、そこに邁進していくエネルギーが生まれるわけだ。
2025年1月10日








