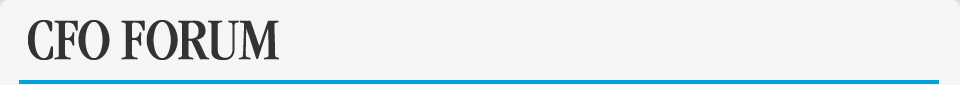
2019年10月15日

グローバル・コミュニケーション
コミュニケーションと前提認識
本名 信行
青山学院大学名誉教授
一般社団法人グローバル・ビジネスコミュニケーション協会代表理事
猿橋 順子
青山学院大学教授
一般社団法人グローバル・ビジネスコミュニケーション協会理事
はじめに
コミュニケ―ションは話し手と聞き手の前提認識に大いに依存する。前提認識を共有している関係では、協調のルールやポライトネスのルールに多少の逸脱があっても、コミュニケーションはなんとか成立する。共有がないと、いろいろな齟齬が生じる。(110号グローバル・コミュニケーション「いろいろなコミュニケーション・スタイル―情報交換と人間関係―」参照)ここでは、コミュニケーションと前提認識の問題を考える。
前提の共有意識
企業内では、社員は社内コミュニケーションについて、多くの前提を共有している。あるいは、共有するものと期待されている。それでも、期待の内容は一様ではない。前回(110号)で考察したケースでは、部長は部下に仕事を依頼したが、完了期限を明示しなかった。部下もそれを聞かなかった。ともに期限については分かっていたつもりであったが、それがくい違っていたのである。
日本人どうしでもこういった行き違いがあるのだから、外国人とのコミュニケーションではもっと、すべてをことばでいうくらいでなければならない。こんなケースがある。日本人の部長は朝礼時に、部下の中国人社員に、明日の会議で使う資料を整理しておくように頼んだ。部下はその場で分かったとはっきりと答えた。
2019年10月15日






