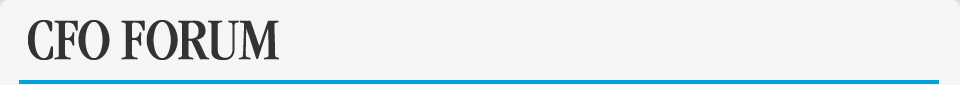
2015年1月15日
小林 喜光 氏
株式会社三菱ケミカルホールディングス 取締役社長
三菱化学株式会社取締役会長
会社の存在意義を突き詰めた先に
三菱ケミカルホールディングス(MCHC)グループは、三菱化学、田辺三菱製薬、三菱樹脂、三菱レイヨン、生命科学インスティテュート、大陽日酸の6つの主要事業会社で構成される企業グループである。機能商品、ヘルスケア、素材の三本の大きな柱で企業経営を進めている。誕生は、2005年10月。三菱化成と三菱油化が合併してできた三菱化学と、その医薬部門をルーツにする三菱ウェルファーマの共同持株会社としてスタート。2007年10月、三菱樹脂を完全子会社化すると共に、田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併して発足した田辺三菱製薬を連結子会社化した。2008年4月、機能材料事業を統合した新生三菱樹脂が発足し、2010年3月には三菱レイヨンとの経営統合を果たした。さらに、2014年4月に新しいヘルスケアソリューション事業を手がける生命科学インスティテュートを立ち上げ、11月には大陽日酸をTOBで連結子会社化した。
私が社長に就任したのは、MCHC発足1年半後の2007年4月だった。
*
企業経営には共通したビジョン、旗印が不可欠である。自動車会社は「四つの車輪に一つのエンジン」、ビール会社は「5%ののど越しのいいアルコール水溶液」をつくるという明確な旗印を持つ。しかし、化学会社はやっかいだ。産業の中で唯一学問の名前を冠し、ミリグラム単位の医薬品からトン単位の汎用化学品まで何万種類もの商品を擁し、全体像がつかみづらい。なんのためにわれわれの仕事はあるのか。皆が一つになり進むべき方向を示す“旗印”は何か――社長就任前、私はそんなことを考えていた。
皆でさまざまな視点から考え抜き、2013年11月にコーポレートブランドとして掲げた御旗が“THE KAITEKI COMPANY”である。KAITEKIが世界共通語となり、グローバルに理念が広まることを願って、アルファベット表記とした。当社の次世代のグローバルな幹部候補たちにも、各種研修などで「基本は効率性追求とROE向上」と収益の最重視を求めながらも、地球と共存する経営を目指す“THE KAITEKI COMPANY”の企業哲学を伝えている。
企業活動で問題解決する手立てを考える
地球は多くの危機を内包している。温暖化に伴う気候変動、人口爆発、資源枯渇、水不足、食糧危機、高齢化といったグローバルな課題を、企業活動で解決する手立てはないか。このまま環境破壊が進めば、地球も人類ももたない。そうした認識をもって、課題へのソリューション提供そのものを社業の中核に据える――それが“THE KAITEKI COMPANY”を実現する“KAITEKI 経営”の根源である。
100年前、空中窒素を固定することでアンモニアの製造を可能にしたのが欧州の化学会社であった。これが化学肥料の原料となり、食糧問題を解決し、世界の人口が増えた。しかし今日では、その人工の窒素酸化物が海を汚し、地球温暖化を促進している。こういった問題を解決するのも、化学会社の責務であり役割であろう。
シェールガスやシェールオイルがリーズナブルな価格で採掘できるようになる以前、今からわずか5年ほど前まで、原油、天然ガス、石炭、果てはウランに至るまで、エネルギー資源は100年経てば枯渇すると言われていた。そこに、埋蔵量300年分と言われるシェールガスが登場し、化石燃料の枯渇に対する危機感が薄まり、今や原油価格も急落の様相を呈している。とはいえ、人類の長い歴史の中で300年という時間はほんの一瞬だ。地球の地下で1億年以上眠っていた化石燃料を凄まじいスピードで使い尽くしていることに変わりはない。言うなれば神が1億年かけてつくった資源を、人間が1年でつくりだすような新しいテクノロジーをいかに開発するか。100億人の生存をかけて、人類の知恵が試されるところである。
近い過去を振り返れば、1960年代頃、化学産業は公害の代名詞だった。しかし、黄色く濁った海が今や澄んだブルーを取戻し、ぜんそくを誘起した街に蛍が舞うまでに大気が浄化されたのも、また科学技術のおかげである。今日、サイエンスの必要性はますます高まっていると痛感している。
そうした状況下にあって、われわれ化学産業は、人類が抱える地球規模の課題に対するソリューションプロバイダーを目指すべき時代がきたと感じている。例えば、車両や航空機を軽量化する部材をつくって燃料消費を減らす、高性能な断熱材で住宅を省エネ化する、あるいは高齢化社会で健康を長く維持できるヘルスケア技術を生み出すといったことが大きなポイントになるだろう。

“differentiation”のための判断基準――競争力確保の鍵
イノベーションには時間と資金がかかる。日本勢が投じた時間と資金に見合う果実を中長期にわたり享受できた時代もあった。例えばDRAMのメモリでは、先行した日本勢は10年、20年のオーダーでゆっくりとシェアを落としていった。しかし、近年は、光ディスク、リチウムイオン電池、液晶テレビ、カーナビなど、あっという間に中国や韓国勢に追いつかれ、シェアを落としてしまう。研究開発に多額の資金を投じても、利益をエンジョイできるのはわずか2~3年というのが実情である。この状況をいかに回避するかが今日の日本の製造業の大きなポイントになっている。
同時に、イノベーションの成功確率そのものも低下している。例えば、創薬では十数年前、候補の化合物1万個のうち1個ぐらいは実際に薬として上市できた。しかし現状では3~4万個に1個程度に確率は落ち、しかも新薬1つを生み出すのに1000億円級の投資が必要となっている。インベンション、イノベーションに要する時間と資金がどんどん膨れ上がっている。
マッキンゼーのまとめによると、化学のイノベーションによって、新しい市場に新しい製品を送り出すのに、平均15年かかっている。今ある市場のプロダクトラインを拡張する程度でも4年かかる。実際、三菱レイヨンも炭素繊維で利益を上げられるようになるまで、約40年の歳月を要している。イノベーションが社会システムに組み込まれ、経済効果を生むには、これほど長い時間がかかる。
このような環境下、もはや日本の製造業のあるべきビジネスモデルは、単に技術や効率を追いかける「モノづくり」ではなく、他とは異なる競争力や価値を創出するための「コトづくり」「ストーリーづくり」の時代に入っているのではないか。そのためには、伝統的な製造業であっても、サービス業的センスとITの活用が求められる。例えば、ハードとソフトを組み合わせて、調達から販売、ブランド展開までのスキーム、物語をつくり上げ、それら全体として利益を上げる、というような方向性だ。アメリカ発の「Internet of Things」や、ドイツの「Industry 4.0」などがモデルケースだろう。モノ単体での消耗戦ではなく、ビジネスモデル全体で付加価値を上げていくことが肝要だ。
日本企業の競争力をめぐる六重苦とも言われるハンディキャップのうち、過度な円高は「アベノミクス」により明らかに修正されたし、労働法制、法人税、通商政策などでも改善の方向が明らかになってきた。しかし、相変わらず日本の大きなハンディキャップとなっていて、しかも改善も見込めないのが、電力などのエネルギーコストと、原料コストだ。例えば韓国やアメリカに比べて日本の電気料金は3倍以上も高い。そうした中で、グローバル市場で戦っていかなければならない。
必ずしもハンディキャップレースを強いられているからとは限らないが、明らかに日本企業のROEはアメリカ、ヨーロッパに比べて極めて低い。財務レバレッジや総資産回転率は欧米並みであるから、まさに低い売上高利益率(ROS)が低いROEに直結していると言える。しかし、日本版スチュワードシップ・コードが動きだし、さらに2015年にはコーポレートガバナンス・コードも示される。日本企業もこのまま低ROS、低ROEに甘んじているわけにはいかない。
グローバルなハンディキャップレースの中で、地球環境のサステナビリティも考慮しながら、日本企業が競争力を確保するには、やはりdifferentiation(ディフェレンシエーション/差異化)以外ないのではないかと思う。
そのために当社が企業活動の判断基準としているのは、「サステナビリティ(環境・資源)」「ヘルス(健康)」「コンフォート(快適)」の三つである。それが、「THE KAITEKI COMPANY」の基盤であり、われわれ素材産業の進む道だと考える。新規事業は、この三つの判断基準に貢献するテーマのみ取り組む。この三つに役立つことで、人類と地球環境のサステナビリティ向上に貢献することを目指すのが、当社の“KAITEKI経営”である。
KAITEKI経営――四象限管理とtransformation
“KAITEKI経営”では、事業をライフサイクルに応じて、①「創造事業」(研究開発を集中して新規に立ち上げる)、②「成長事業」(経営資源を集中投入してさらなる収益拡大を狙う)③「基幹・中堅事業」(限定された資源投資で安定した収益基盤を担う)、④「再編・再構築事業」(撤退も含めて事業構造を改革し、効率的な展開を目指す)の四つに分類し、「四象限管理」という事業管理手法でポートフォリオ・トランスフォーメーションを制度的に推進している。基幹・中堅事業から得られる経営資源を成長事業や創造事業に戦略的に投入していくことで、常に新たな価値を創造し続け、グループとしての持続的な成長を目指している。
トランスフォーメーション推進のため、M&Aにも積極的に取り組んでいる。創造事業(イノベーション)は時間がかかり資金もかかる。研究開発の成果が見えるのは先のことにならざるを得ない。これに対してM&Aは、直ちにポジティブな結果となってあらわれる。
グローバル化が進み、新しいビジネスがあっという間に追い付かれ、飽和する時代にあって、「オープン・シェアード・ビジネス」という手法が求められるのではないかと考えている。研究開発段階から、材料、製造、サービス、販売チャネル、ブランドに至るまで、自社の強い部分はブラックボックス化してクローズし、弱い部分は早めにオープンにして強いパートナーとコラボレーションする。そして、ビジネスの全体系として最も素早く、効率良くやっていく。研究開発だけに限った「オープン・イノベーション」ではもはや不十分というのが実感だ。

KAITEKI経営――数値化できないものを数値化する
私が社長に就いたのは、2007年4月。その1年半前の2005年10月、研究開発担当常務(CTO)としてグループ全体の研究開発部門を統括していた私は、「プロジェクト10/20」をスタートさせた。研究開発は何をテーマに選択するかが最も重要だ。そもそも「WHAT」が間違えていたら、いくら「HOW」を議論しても無意味になる。そのため、10年、20年先の社会が必要としているものを見据えて、そこからバックキャストして現時点の研究開発テーマを選ぶことにしたのがこのプロジェクトである。そこからあぶりだされた判断基準が、「サステナビリティ」「ヘルス」「コンフォート」だったわけである。
さらに2009年4月には、単に科学技術だけではなく、社会科学的なアプローチも含めて未来のビジネスのシーズを探索するシンクタンク兼研究所の、「地球快適化インスティテュート」を設立した。
“THE KAITEKI COMPANY”を実現するための“KAITEKI経営”では、①ROEを中心として、資本の効率化、収益向上を追求する経営学軸(Management of Economics軸)、②イノベーション創出を追求する技術経営軸(Management of Technology軸)、③企業活動を通じて環境・社会課題の解決に貢献し、人類のサステナビリティ向上を追求する軸(Management of Sustainability軸)の三つの軸からなる三次元的、総合的な企業価値の総和の拡大を図っている。同時に、「時代の風」とでもいうべき④時間軸もしっかり考慮する(四次元経営)。
①はCFO、②はCTO、そして③はCSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)がそれぞれ担当する。これら三つのベクトルを合成したところに本当の企業価値「KAITEKI価値」が生まれ、その責任はCEOが負っている。このように三次元的に全体を整理すると社員の理解も進むし、アクションもとりやすくなる。
“KAITEKI経営”のポイントは、一般的には数値化できないと思われているものを、蛮勇をふるって数値化するところにある。数値化せず、定性的にどれほど議論を重ねても前には進まないからだ。
①の経営学軸は売上高や各種利益、ROE、ROSなど、制度的な数値化の方法が存在しているが、③のサステナビリティ軸については数値化の先例がない。そのため、当社は独自に「サステナビリティ」「ヘルス」「コンフォート」というインデックスを設定してそれぞれ数値化し、目標と現状を定量的に評価して点数をつける取組みを行っている。例えば、CO2排出量については、2005年から30%削減するという2015年の目標を、現状すでに達成している。これを点数にすればみごと満点、といった具合である。
そのうえで、グループ各社や個人の業績評価においても、①の経営学軸の実績だけでなく、③のサステナビリティ軸の点数も用いている。ボーナスの査定にもサステナビリティ軸の成績が反映されるわけだから、当然社員は本気になって取り組むことになる。
*
たった数年で世界は驚くほど変わる。企業は日々もがきながら経営の継続性に努めている。しかし、なによりも地球との共存なくしては、人も社会も、当然企業も永続しようがない。地球と共存するKAITEKI経営にグループ一丸となって取り組み、21世紀を共に勝ち抜き、生き抜いていきたい。
本日はご清聴ありがとうございました。
※本稿は、2014年12月2日開催の「第14回CFOフォーラム・ジャパン2014」の講演内容を編集部にてまとめたものです。
2015年1月15日









