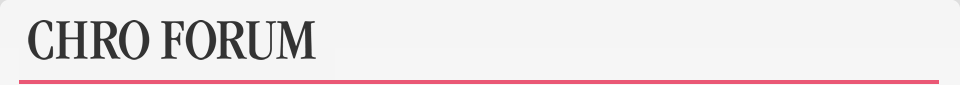
2025年1月10日

GLOBAL MANAGEMENT グローバルマネジメント
HRジャーナリズム 人的資本経営のその先へのヒント
CHRO力その60:CXOsの新リベラル・アーツを鍛える1
伊藤 武彦
NUCBビジネススクール 教授
前回は、AIを起点とした更なる変化に耐える経営をしていく上で、CXOsの能力向上はCHROが気にするべき課題である。そして、CXOsはその先のキャリアオプションの1つである取締役人材の育成まで睨んで行う必要があるということを議論した。
CXOsは時間がなく、しかも全社的に速攻的な効果、アウトプットが期待されている。その前提から、CHROがこのデザインのイニシアチブを握り、推進することが必要であり、学んだこと、能力が向上したことが経営の現場でリアルに反映することで企業の成長をサポートする必要がある。
そこで、CXOsの新リベラル・アーツとして4つの言語を強化するという議論を開始している。前回はその第1の経営に関する言語であった。今回は第2の株主(投資家)に関する言語である。
2025年1月10日








