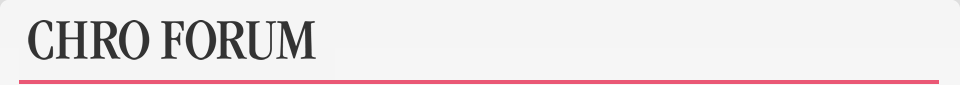
2019年7月1日
●かつて日本のHRは事業の近くにあった
――日本の人事の在り方が問われています。
2018年11月、ニューヨークで開催されたCHROラウンドテーブルという、IBM等グローバル企業のCHROが10人ほど集まり自由に議論する会で、CHROは、まず事業の方向性を示して、それに沿った人事施策を実施することが必要という議論をしましたが、MicrosoftとAmazonのCHROは2人とも女性エンジニアで事業部門出身の方でした。おそらく、「事業を知らずして人事はできない」という評価が欧米のトップ企業でなされ始めているのだと思います。それに比較すると、日本企業は人事が少し事業から遠くなっているように思えます。
私が日立に入社した1983年当時、人事は事業とかなり近いところにありました。事業と人事について工場長や設計部長とよく話し合ったものです。1988年に米国で1年間研修したとき、米国でのHRの仕事は採用面接のファシリテート程度。この経験は衝撃でした。ちょうど、“Japan as No.1"と言われた時代で、日本国内のマーケット自体が大きく成長しており、その製品を海外に輸出してシェアを伸ばしていました。日立で言えば、顧客が日本電信電話公社(現在のNTTグループ)や日本国有鉄道(現在のJRグループ)、電力会社などの大手顧客によって安定した売上を確保していました。ある程度優秀な技術者を多く持つ会社であれば仕事がなくなることはなく、その中で人事施策は安定を求め、長期雇用や年功制が機能しました。私が入社した当時は、団塊の世代が40歳になり始めポストが不足していました。この人たちにやる気を持って技術開発等を続けてもらうために、人事部門は資格制度をつくり出し、ポストと無関係にある程度処遇する方法を見つけ出しました。
もう一つは製造現場での人事施策です。80年代当時は、製造現場はほぼ日本にありました。日本の現場の人のモチベーションをいかに上げるかが事業にとって重要なことで、日立で言えば「工師制度」(技能系職種の最高位。各工場に数人程度のみ)をつくって現場の優れた技能者を優遇しました。例えば、賞与支給日は工場長室に工師を招いて、社長寸志を工場長が社長に代わって手渡ししていました。これによって「日立は現場を大事にしてくれている」と皆が感じ、現場の士気は非常に高まりました。
このように、当時の人事施策は事業に合致していました。ですから80年代の日本は、事業に近い人事であったと私は思っています。
ところが、その後米国は日本に学んで急速に人事部門を強化し、逆に日本はそこに安住してしまい昔ながらの制度を運用し続けました。環境が激変し、ものづくりの現場は世界に移り、かつてのように製品力だけでは勝てなくなったとき、当然、人事も変革しなければならなかったのですが。
2019年7月1日







