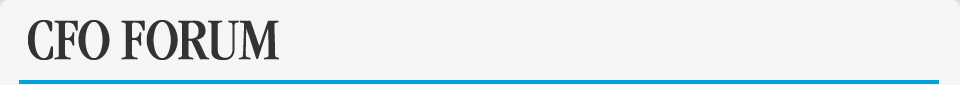
2024年12月16日

財務マネジメント・サーベイ
経営管理(FP&A)機能強化の現状
Ridgelinez株式会社
はじめに
昨今の環境変化に対応するために、企業には経営管理領域の変革がより一層求められているが、必要性を感じつつも、旧態依然とした制度・仕組みからの脱却が困難、ステークホルダー間の手間のかかる利害調整、強いリーダーシップを発揮して推進するリーダー人材の不足等の理由で着手できていない企業も多いと思われる。
特に、近年注目を浴びているFP&A人材を集約した組織や経営管理人材の育成は、中長期での取り組みになるため、関心はあるもののスタートできていない企業が多いとみられる。
企業経営を取り巻く環境の複雑性が増す中で、現時点における日本企業の経営管理の状況を把握するという目的で、2024年8月に一般社団法人日本CFO協会とともに経営管理(FP&A)機能強化の現状に関するアンケート調査を行った。
本調査を通じて、日本企業における経営管理高度化に向けた取り組みを分析・考察し、今後の推進についての示唆を提供する。
2024年12月16日








