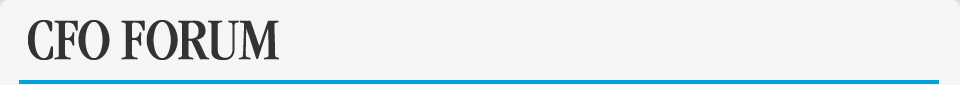
2017年6月15日
企業年金の
フィデューシャリー・デューティー
森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
金融庁の森信親長官は、2017年4月7日の講演において、主として投資信託を念頭において資産運用業界の抜本的改革を極めて厳しい口調で求めたのだが、そのなかで企業年金の資産運用についても注目すべき発言をしている。企業年金は厚生労働省の所管であって、そこに金融庁長官が言及することは極めて異例のことであるが、背景に何があるのか。
森長官による問題提起
金融庁が公表している正式な講演録によれば、森長官は次のように発言したのである。
「運用会社だけでなく、アセットオーナーの役割も重要です。例えば、年金基金には、掛け金をかけている国民に対するフィデューシャリー・デューティーを十全に果たすことが求められます。アセットオーナーは、自らの資金を委託するのに最もふさわしい能力を持った運用会社を見極める必要がありますが、仮に企業年金が、運用のマンデートを運用会社グループとのリレーションで与えているとすれば、それはフィデューシャリー・デューティーの観点に照らして問題があります。
アセットオーナーとしてのクオリティが高く、中長期的に素晴らしい運用成績を挙げている米国の大学の基金や年金基金には、例外なく、優れた目利き力、運用能力を持った責任者がいます。我が国の企業年金についても、企業内の人事異動でなく、プロとして適切な能力・判断力を有した責任者を内外の幅広い候補者から選び、配置することが望まれます。アセットオーナーとアセットマネージャーの双方が共に本源的な実力を高め、究極の受益者である国民に対するフィデューシャリー・デューティーを果たしていくことが、日本の運用業界の成長につながるのだと思います」
アセットオーナーのフィデューシャリー・デューティー
この講演は、資産運用関連の業務に従事する者を対象にしてなされたので、自明のこととして専門用語が使われている。
アセットオーナーとは、投資運用業者の顧客のことで、投資信託ならば個人投資家、投資一任契約ならば企業年金等の主に機関投資家である。フィデューシャリー・デューティーとは、専らに顧客のために働くという理念に帰着し、そこに二つの要素を含む。一つは、職務の遂行において自己もしくは第三者の利益を一切顧みないという厳格な忠実義務であり、もう一つは、顧客の利益の最大化のために専門家として最善を尽くすという高度な注意義務である。
さて、アセットオーナーには顧客がないわけだから、フィデューシャリー・デューティーを論ずる余地はないようにみえる。しかし、企業年金の場合には、資産運用の成果は、最終受益者、即ち制度の加入員と受給者に帰属するから、フィデューシャリー・デューティーを負うのでなくては最終受益者の利益が守られなくなる。森長官は、この重大な論点を指摘したわけだ。
企業年金の貧困なる実態
同時に、森長官の発言は、はからずも、日本の企業年金の貧困なる実態を暴露したことになる。
「仮に企業年金が、運用のマンデートを運用会社グループとのリレーションで与えているとすれば」という表現は、仮定形をとってはいるが、言語理解の常識として「企業年金が、運用のマンデートを運用会社グループとのリレーションで与えている」という事実認識の婉曲表現であると考えるべきである。
また、「我が国の企業年金についても、企業内の人事異動でなく、プロとして適切な能力・判断力を有した責任者を内外の幅広い候補者から選び、配置することが望まれます」は、単なる希望の表明ではなく、企業年金の資産運用管理者の選任が不適切である実態の指摘と解釈すべきである。
つまり、森長官は、運用会社の選択においては、企業と銀行等の金融機関との親密な関係に基づいていることから、忠実義務違反の実態があり、資産運用管理者の選任においては、企業の人事の都合が優先して、少しも専門的知見を持たない人が選ばれていることから、注意義務違反の実態があることを指摘しているのであって、要は、企業年金のフィデューシャリー・デューティー違反の実態を暴露しているのである。
顧客本位の業務運営に関する原則
ところで、講演に先立つ3月30日に、金融庁は、資産運用関連事業の改革のために「顧客本位の業務運営に関する原則」というソフトローを公表している。そこでは、フィデューシャリー・デューティーという言葉は使われなくなっているが、原則の公表前までは、「顧客本位の業務運営(フィデューシャリー・デューティー)」と表現されていて、二つは同じものとして説明されていたのである。
さて、この原則はソフトローであって、金融庁が定める規制ではない。しかも、原則の策定過程においては、対象が広く資産運用関連業務に従事する不特定の金融事業者とされていることについて、異論があったにもかかわらず、対象を特定しないほうがいいとする金融庁の強い意向が通った経緯がある。
資産運用に関連する事業を営んでいれば、金融庁の所管法人でなくとも、金融事業者になる。だとすると、資産運用を行う企業年金が金融事業者になり、原則の対象となることに疑う余地はない。ならば、原則の主旨に賛同する企業年金において、積極的にコンプライすることは自由である。逆に、主旨に賛同できないということなら、コンプライしないことも自由だし、そもそも原則は自分に適用がないと思うなら、コンプライしない理由をエクスプレインする必要もない。
しかし、コンプライする企業年金が一つでも出てくると、コンプライしない企業年金の加入員や受給者のなかに疑念を生じるであろう。そういう疑念を持った加入員や受給者は、自分の属する企業年金に対して、コンプライしない理由のエクスプレインを求めることになるのではないか。
「見える化」を通じた改革
そのとき、企業側は、運用会社の選定に際しては銀行等の借入先や大株主である金融機関との友好関係の維持を考慮するとか、定年退職者や役職定年者のための職場確保として企業年金の管理者を選任しているとか、そういう説明をできるはずもない。
説明できない現状を放置するならば、企業として社会的に通用し得ない低次元のコーポレートガバナンスの実態を証明するようなものだから、是正の努力は必ずなされる。森長官は、そういう力の働き方を「見える化」を通じた市場原理としてとらえ、それを行政課題の実現手法にしているのである。
原則に率先してコンプライする会社は、間違いなく超優良企業である。ある会社がコンプライすることで超優良企業である事実を「見える化」する、そうすれば他社も「見える化」の努力を促される、その切磋琢磨が改革を推進する、これぞ森長官流の行政手法なのである。
2017年6月15日






