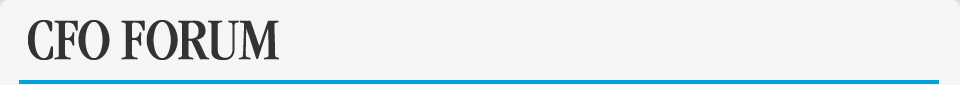
2017年8月17日
利益相反は論外、
利益相反の可能性こそが問題
森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
利益相反とは何か、この本来は自明であるべき問いについては、未だかつて真剣に問われたことがない。実際、利益相反の事実が認定されたことなど皆無に近いのである。しかし、他方では、幅広い領域で利益相反のおそれのある事態が横行していることについては、常に指摘されてきた。
利益相反のおそれが蔓延していても、利益相反の事実が問題にされないのは、利益相反のおそれと利益相反自体は異なるものであり、おそれがおそれに止まる限り、利益相反ではないと考えられているからである。しかし、こうした論法は、常識からすれば詭弁ではないか。
おそれは可能性のことである。可能性には、二つの意味があろう。一つは、まさに可能性で、利益相反を発生させる温床を形成しているという意味、もう一つは、事実としては利益相反を立証できないが、裏には利益相反の存在を推定させるという意味である。もちろん、より重要なのは後者であって、これは限りなく利益相反そのものに近い状態なのである。
企業年金における利益相反のおそれ
では、企業年金の資産運用における利益相反のおそれを例にして検討しよう。利益相反とは忠実義務違反のことであるが、企業年金の根拠法である「確定給付企業年金法」は、受益者に対する関係で企業年金の忠実義務を定めているのである。したがって、法律上、企業年金の運営において母体企業の親密金融機関との関係を重視することは、母体企業の利益を図ることとなり、忠実義務に違反するおそれを生じるわけだ。
この点については、厚生労働省年金局長通知に、「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」というものがあって、そこに、忠実義務違反のおそれとして、企業年金の運用委託先に母体企業と緊密な関係にあるものが選ばれている場合が挙げられている。具体的には、大株主の生命保険会社、その子会社の投資運用業者、借入先の信託銀行、借入先の銀行の子会社の投資運用業者が選ばれる事態を指しているのである。
ところが、通知は、忠実義務違反のおそれが事実としての忠実義務違反になるためには、運用委託先の選択に際して、母体企業の親密先だという理由以外に合理的な理由がない、不当に運用委託先に有利な契約になっているなどの付帯する事実の立証が必要になるように書かれている。これでは、現実には、忠実義務違反の事実の立証など、ほぼ不可能だ。
故に、企業年金の忠実義務違反のおそれは放置され、ごく普通の悪弊として蔓延しているのである。ここには、厚生労働省の怠慢行政もあるのだが、忠実義務違反、あるいは利益相反に関する一般的な理解の限界が露呈している面もあるのだ。
金融庁長官による問題提起
ここに切り込んだのが金融庁の森信親長官だ。長官は、4月7日の講演において、「仮に企業年金が、運用のマンデートを運用会社グループとのリレーションで与えているとすれば、それはフィデューシャリー・デューティーの観点に照らして問題があります」と発言したのである。
「運用のマンデート」は運用委託契約のことであり、「運用会社グループとのリレーション」というのは、企業年金の母体企業がもつ取引先金融機関との親密な関係をいう。
フィデューシャリー・デューティーというのは、企業年金の資産運用は、専らに最終受益者、即ち企業年金の加入員である現役の従業員と既に退職して年金を受給している人の利益のためになされるべきだという理念である。当然、そこには、母体企業の利益を一切顧みないという厳格な忠実義務を含む。
つまり、森長官の発言を翻訳すれば、企業年金が資産運用の委託先を選任するに際して、母体企業がもつ金融機関との親密な関係を判断基準とすることは、それが必ずしも法律上の忠実義務違反とはならないとしても、フィデューシャリー・デューティーには反すると言っているのだ。
金融庁のいうフィデューシャリー・デューティー
フィデューシャリー・デューティーは、金融庁の資産運用関連事業における施策として、3月30日に、「顧客本位の業務運営に関する原則」に具現化されている。そこに7原則あって、第3原則は「利益相反の適切な管理」と題されたもので、「金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである」とされている。
こうして、少なくとも金融行政においては、金融事業者に対し、伝統的な忠実義務に関する理解のもとで放置されてきた利益相反のおそれは、より厳格なフィデューシャリー・デューティーのもとで、利益相反の可能性として、防止に向けた対策が求められるに至ったのである。
したがって、森長官の発言の趣旨は、法律上、忠実義務違反のおそれ、即ち可能性に留まる事態も、それが利益相反の可能性である限り、より高度な義務であるフィデューシャリー・デューティーには反するということなのである。要は、フィデューシャリー・デューティーのもとでは、違反の可能性に留まることも違反と同等だということだ。
金融事業者としての企業年金
さて、問題は金融事業者の定義だが、金融庁は、「顧客本位の業務運営に関する原則」の策定に際して、対象を特定しないで資産運用関連事業を営むものを幅広く含める趣旨で、金融事業者という言葉を採用したのである。故に、対象は、法令の根拠に基づいて金融庁が所管する法人に限られず、企業年金も含むと考えることに妨げない。
しかも、この原則はソフトローであって、法令に基づいて金融庁が制定した規則等ではないから、コンプライ、即ち採択して自己を律する規範とすることも、エクスプレイン、即ち理由を説明して採択しないことも、金融事業者の判断に委ねられる。企業年金基金や母体企業が自らを金融事業者の自覚のもとで自主的にコンプライすることは自由だし、原則の対象外だと思うなら、コンプライしない理由をエクスプレインすることなく無視することも自由だ。
もちろん、原則へ積極的にコンプライする企業は、ガバナンス面で一流企業であることを証明することになる。仮に、それが有名大企業で、大きな社会的反響を呼ぶとしたら、他の企業はガバナンス面で二流であることを証明することになり、対応を促されることになる。
実は、金融庁は、こうした社会の監視が働いて自浄作用が進むことを「見える化」と呼んでいて、行政課題の実現手法に位置付けている。おそらくは、森長官の発言の裏には、企業の自主的な対応についての単なる楽観的な期待を超えて、「見える化」による外圧を働かせる意図があるのだ。
2017年8月17日






