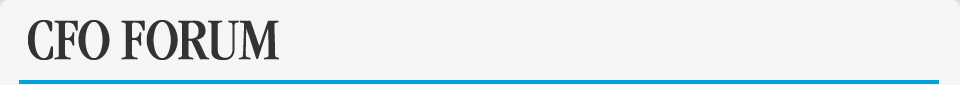
2022年7月15日

グローバル・コミュニケーション
言語政策を考える枠組み
猿橋 順子
一般社団法人グローバル・ビジネスコミュニケーション協会理事
青山学院大学教授
本名 信行
一般社団法人グローバル・ビジネスコミュニケーション協会代表理事
青山学院大学名誉教授
日本の言語政策不在論
一般論として、日本には言語政策がない、あるいは明瞭かつ戦略的な言語政策が存在しない、という指摘を聞くことがある。これらの指摘には、主に以下の3つの言語面の特徴や課題が関連していると考えられる。
第一に、日本語は表記の面において自由度が高い。読点をどこに打つかは、読み手の理解を助けるためだけでなく、書き手の呼吸や強調点を表現するためにも吟味される。また、漢字かひらがなのどちらを用いるかについても、想定する読者の年齢層や、公式な文書か私的な文書かといった用途に加え、書き手の伝えたい印象に応じて選択される。カタカナは外国語から語を借用する際はもちろんのこと、まさに「イミ消費」という例のように、新しい意味を付与したいときなどにも用いられる。ちなみに、「イミ消費」とは、製品の背後にあるストーリーに共感して行われる消費のことを指す。
2022年7月15日






