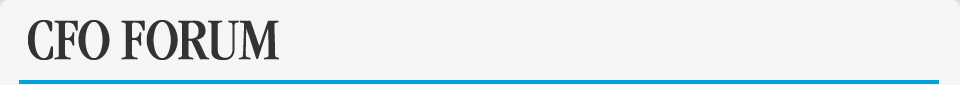
2020年10月15日

グローバル・コミュニケーション
ダイバーシティと手話言語
本名 信行
青山学院大学名誉教授
一般社団法人グローバル・ビジネスコミュニケーション協会代表理事
猿橋 順子
青山学院大学教授
一般社団法人グローバル・ビジネスコミュニケーション協会理事
企業と手話
企業や行政は、いろいろな意味でマイノリティの立場にある人びとの、社会参加を支援する義務がある。彼らを雇用したり、顧客として適切に対応できる環境を整備することが求められる。ここでは、ろう者(聴覚障害者)に焦点を当てて話を進める。ろう者はろう者どうしの、そして健聴者とのコミュニケーションで手話言語を必要としている。
手話はろう者の母語といってもよい。ろう者は家庭、学校、職場などで、自由で、創造的な生活を送るために手話を使い、さらに手話のできる健聴者のアシストを求めている。特に、企業や行政では、手話のできる人材を雇用し、適切に配置する工夫が期待される。
手話とは何か
手話の意義をしっかりと考えるためには、人間の言語とはどういうものか、そしてろう者にとって手話とはどういう言語かについて、十分に理解し、確固たる知識をもたなければならない。人間は生物学的特徴として、「言語」をもって生まれてくる。失聴はこの「言語」とはほとんど関係がない。聞こえを失うと話しことばの習得は困難になるが、そのかわりに手話の獲得を促す。
2020年10月15日






