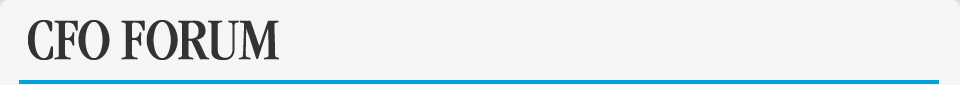
2022年8月18日

Focus
「ダボスマン」の変遷
朱 穎
アメリカデューク大学客員研究員
パリESLSCAビジネススクール経営学教授
ダボス会議は、今年の5月に2年ぶりにスイスの高級スキーリゾート地で開催された。パンデミックの影響もあり、開催時期が1月から5月になったためか、参加者は前回の3,000人から2,000人に留まった。世界で最も有名なメガカンファレンスは、その豪華な場所と参加者の多さから、近年は当然ながら多くの批判も集めている。その最も典型的な例が「ダボスマン」である。
「ダボスマン」という言葉は、政治学者のサミュエル・ハンチントン氏が、スイスの町ダボスで開催される世界経済フォーラム(World Economic Forum=WEF)の年次総会の参加者のうち富裕層の一部を指して命名したものである。毎年、メディアによって復活させられているが、「ダボスマン」は世界が燃えている間、意気揚々と語っているというイメージがテレビ中継でも確認されている。何十年もの間、「ダボスマン」という概念は、金持ちで、疎外され、自国のルーツから切り離され、空疎なレトリックに満ちているという批判を集めてきた。特に、21世紀に入ってから、トランスナショナルなエリートは、結局は空っぽの話し相手であるというステレオタイプが定着してしまい、ニューヨークの有名なジャーナリストが最近出版された本の中で、このステレオタイプの「ダボスマン」に対して、激しく非難しているのも有名な話である。
2022年8月18日






