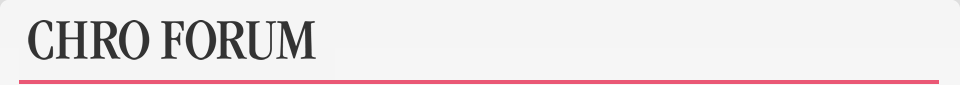
2025年7月1日

人事マネジメント・サーベイ
従業員エンゲージメント調査結果
株式会社U-ZERO
はじめに
近年、人的資本経営やウェルビーイング経営といったキーワードが注目を集める中で、従業員エンゲージメントは、企業の持続的成長を支える戦略的資産として位置付けられるようになってきた。多様な働き方や価値観が共存する現代において、従業員一人ひとりが「この職場で働き続けたい」、「ここで成長できる」と実感できる環境づくりは、経営の最重要課題の1つである。
本調査は、株式会社U-ZEROが日本CHRO協会の協力により実施した「従業員エンゲージメント調査」の結果をもとに、企業におけるエンゲージメントの実態とその影響要因を明らかにすることを目的として実施された。エンゲージメントに関する設問の単純集計を通じて、現場のリアルな声や傾向を可視化している。
[調査の概要]
テーマ:従業員エンゲージメントの現状と課題
サンプル数:218
調査期間:2025年1月7日~1月28日
調査方法:インターネットリサーチ
対象:日本CHRO協会の会員であり、人事担当者、人事責任者
※本調査では小数点第1位で四捨五入しているため、足し上げても合計数値が100%とならない場合がございます
エンゲージメントは重視されているのに、なぜ実行に結びつかないのか?
■キーインサイト
エンゲージメントの重要性は多くの企業で認識されているが、リソース不足や体制のばらつきにより、施策の実行や定着には課題が残る。
■提言
経営指標としての組み込みや、人事部門だけに頼らない横断的な推進体制の構築が求められる。
「エンゲージメントを高めることが企業成長に直結する」という認識を持っている経営層が多数を占めていることがわかった(図1)。また、人事部門においては、経営層と同様にエンゲージメントの重要性を認識しているだけでなく、より実務的な視点から、その必要性・重要性を強く感じている傾向が見られた(図2)。
本調査では、多くの企業が「エンゲージメントを高めることの重要性」を認識している一方で、実際のリソース(予算・人員など)の配分が十分とは言えない現状も浮き彫りになった(図3)。
また、エンゲージメントの運用体制や責任の所在には企業ごとの差があり、人事主導のケースだけでなく、事業部門が中心となって推進している事例も見られた。これは、エンゲージメント推進における体制の多様性を示している(図4)。
さらに、経営層の評価指標にエンゲージメントを組み込んでいる企業は依然として少数にとどまっており、経営レベルでの制度設計はこれからの課題と言える(図5)。
従業員エンゲージメントの可視化を目的として、エンゲージメントサーベイを実施している企業は全体の約8割に上り、エンゲージメントへの関心の高まりがうかがえる(図6)。
しかしながら、その結果をもとに具体的な施策へとつなげられている企業はまだ限定的であり、実行段階に課題を抱えている実態が明らかになった(図7)。さらに、エンゲージメントサーベイの意義について懐疑的な見方もあり、1割以上の回答者が「意義を感じていない」と回答している(図8)。
今後は、エンゲージメントサーベイのデータをいかに分析・活用し、具体的なアクションプランに落とし込んでいけるかが、エンゲージメント向上の鍵を握ると言えるだろう。
なぜ“声を聴く姿勢”があっても、フィードバックは活性化しないのか?
■キーインサイト
フィードバックや従業員の声の重要性は広く理解されているが、実際の運用には温度差があり、制度設計・文化の双方に課題がある。
■提言
継続的にフィードバックが循環する仕組みと、経営層が積極的に現場の声を取り込む態度変容が求められる。
フィードバックの重要性については、96%の回答者がその意義を認識しており(図10)、91%が「自社にも取り入れたい」と考えていることがわかった(図11)。しかしながら、実際に「フィードバックが活発である」と答えた企業は全体の約4割にとどまり、認識と実態との間に大きなギャップがあることが示されている(図12)。
本調査では、「従業員の声を経営に取り入れることは重要である」と考えている割合は、人事部門で98%(図13)、経営層でも86%(図14)と、非常に高い水準に達していることがわかった。これは、組織の健全性や持続的成長において、現場の声が欠かせないという共通認識が広がっていることを示している。
一方で、実際に「従業員の声が経営に反映されている」と回答した企業は約半数(54%)にとどまっており、こちらもフィードバックと同様に認識と実行の間には一定のギャップが存在している(図15)。
組織風土はなぜ対話的になりにくいのか? そして“壁”はなぜ残るのか?
■キーインサイト
対話が生まれにくい組織文化と部門間の「壁」が依然として業務遂行に大きな影響を及ぼしている。
■提言
心理的安全性を支える組織文化づくりと、部門を越えた連携・共通KPIの導入などの構造的対策が必要。
自社の組織風土について、「抱え込んで沈黙する」と回答した割合は45%、「中傷や陰口が多い」は16%と、望ましい状態である「建設的に伝え合う」風土だとしたのは39%にとどまった(図16)。これは、健全な対話が十分に根付いていない実態を示している。
さらに、「組織の壁がある」と感じている人は全体の87%に上り(図17)、そのうち89%が、こうした壁が「業務に弊害をもたらしている」と回答している(図18)。部門間の連携不足や情報断絶が、日常業務に具体的な影響を与えていることがうかがえる。
一方で、こうした課題に対して前向きな姿勢も見られた。75%の回答者が「改善するつもりである」と答えており(図19)、さらに86%の企業では、すでに何らかの改善に向けた取り組みを実施していると回答している(図20)。
この結果は、組織の壁が依然として大きな課題である一方で、多くの企業がその解消に向けて具体的なアクションを起こし始めていることを示している。今後は、こうした取り組みを継続的に進化させ、実効性のある変化へとつなげていくことが求められる。
終わりに
本調査からは、エンゲージメントの重要性が広く認識されている一方で、その実行・定着には、まだ多くの課題が存在していることが明らかになった。今後は「測る」だけではなく、「活用する」ための体制構築や、データの分析・施策への反映といった実践的な取り組みがますます重要になる。
本レポートが、貴社におけるエンゲージメント強化のためのヒントや、人的資本経営の推進に向けた一助となれば幸いだ。
株式会社U-ZEROについて
株式会社U-ZEROは、「すべての人が幸せで“働きがい”のある未来へ」を掲げ、日本のエンゲージメントを2024年の6%から2030年に10%、将来的には世界平均の23%へと引き上げることをミッションとするスタートアップです。経営と従業員が対話を重ねながら価値を共創する 「エンゲージメント共創経営」 の実現を目指し、「デジタル」(AIを活用したクラウドサービス)、「コンサルティング」(チェンジマネジメント支援)、「エンパワーメント」(研修など人的サービス)という3つのソリューションで日本企業のエンゲージメント改革を後押ししています。詳細については以下のサイトをご覧ください。
2025年7月1日


























