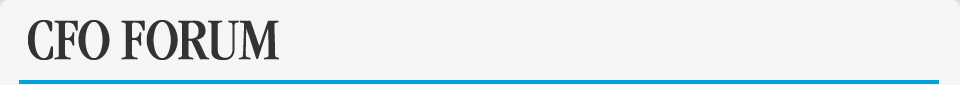
2014年9月16日
- パネリスト(ご氏名50音順)
-

池永朝昭 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士

榎本俊彦 氏
日本精工株式会社 執行役財務本部副本部長

髙橋光夫 氏
株式会社ドンキホーテホールディングス 専務取締役

藤田純孝 氏
日本CFO協会 理事長
元伊藤忠商事取締役副会長
三田慎一 氏
元花王株式会社 取締役執行役員会計財務部門統括CFO
日本CFO協会理事 - コーディネーター
-

森本親治 氏
新日本有限責任監査法人 GRC推進室長
シニアパートナー 公認会計士
森本 企業統治強化の方法は、規模、業種、業態によって全く異なってきます。本日お集まりいただきましたパネリストの方々も、日本精工(NSK)様は、B to Bの自動車分野ですから、製品企画や品質管理はグローバルスタンダードできっちり行う姿勢をお持ちです。一方、花王様は、一般消費財なので、各国の地域性や市場対応が非常に重要になってきます。ドンキホーテ様は、完全に流通業でございますので、現地現品で各顧客対応が最重要になってきます。このようにグローバルの中にある各業態各社の統治はどう図ればいいのでしょうか。また、伊藤忠様のような総合商社の場合は事業形態が多岐にわたり、子会社数も非常に多くなっています。そうした巨大グループをどう統括すればいいのでしょうか。それぞれ異なる観点がありますので、パネリストの皆様から実務経験に基づいた経営統治の強化の必要性、あるいはその適用方法に関してお話を伺いたいと思います。

国際規制や会社法上の内部統制構築責任から見た経営統治の必要性
森本 まずは、国際規制や会社法上の内部統制構築責任から見た経営統治の必要性から、始めさせていただきたいと思います。
経営統治の重要性について藤田様のお話にもありましたが、まずは受託経営責任を履行していくためには、グローバル事業全体を掌握しなければなりません。原点は業務にあります。ただ、そのベースは、まずは法的な責任であることが非常に多いと言えます。一方、企業で経営統治強化の必要性を痛切に感じるのは、やはり不正や不祥事がトリガーになることが圧倒的です。まずは、規制対応、法令遵守の観点から経営統合の問題に入っていきたいと思います。
「内部統制」は、財務報告統制であるという暗黙の前提のようなものがありました。そのため、業務の目的やコンプライアンス目的まで意識して「内部統制」という言葉を使うケースは非常に少ないように思います。しかし、本日の三田様、榎本様のお話ではほとんど財務報告、連結財務報告についての話はなく、むしろ業務効率やコンプライアンス面でのお話が圧倒的に多かったと思います。ですから、まずは出発点としての内部統制の目的の違いを認識していただきたいと思います。
会社法上、内部統制の構築責任と言ったとき「内部統制」は財務報告の統制だけではありません。経営全般にわたって業務執行を図るうえでの適法性や効率性など、業務執行に関するさまざまな統制と、対象目的が幅広くなっています。まず、独禁法や反トラスト法、海外不正支払防止法(いわゆるFCPA)の企業法務に関する豊富な実務経験をお持ちの池永先生にお聞きしたいと思います。金商法では、財務報告統制だけに限る場合が多いのですが、一般的に会社法上求められる内部統制の構築責任についてお話しいただけますか。
池永 会社法上は、取締役の善管注意義務の一環として内部統制構築の責任が認められているという構造になっています。本日のテーマの「グループ経営統治力」という観点から、判例と今回の会社法改正の中身を見ますと、規制の強化といいますか、取締役の責任はますます厳格に重くなる方向性が出ていると思います。
まず会社法関係では、会社法の改正案で重要な改正がいくつか提案されています。第1は「取締役会の監督機能の強化」。第2は「会計監査人の選任・解任等に関する議案の内容の決定権を監査役に移す」という制度設計。第3は「資金調達場面における企業統治のあり方の新たな制度の導入」。そして、本日のテーマと深くかかわるのが、第4の「親子会社に関する規律の強化」です。親会社の株主を主眼として、多重代表訴訟制度をはじめとするいくつかの制度が提案されています。中でも、「企業集団の業務の適正を確保するための体制に関する取締役会の決議の制度化」が、比較的重要だと思っています。
その意味は、判例の中で取締役の内部統制構築義務がどう考えられているかをお話しするとわかりやすくなります。まず判例上は、取締役の善管注意義務について、「責任がある。義務がある」という点ではどんどん厳格化していますが、経営判断の原則を適用しつつ、実際の具体的な場面においては責任を認定しないというような原則的な流れがあり、他方において例外的に厳格に判断することがあったというのが、ざっくりした判例の流れかと思います。
内部統制構築義務の判例① 大和銀行代表訴訟事件
池永 内部統制構築義務について代表的な判例と言われるのが大和銀行の代表訴訟事件です。内部統制の構築、いわゆるリスク管理体制の構築義務が裁判上正面から取り上げられた判例です。これについて大阪地裁は、リスク管理体制のレベルについては、「裁判時点で求められているリスク管理体制の水準をもって判断してはならない」「行為が発生した当時のリスク管理体制の水準から見て、内部統制、リスク管理体制というのが適切に構築されていたのかどうなのかということを判断する」という基準を示しました。大和銀行事件とは、1人の財務省証券(USトレジャリー)のトレーダーが、トレードしながら、かつ管理者の立場も兼任しており、損失をいわゆるダミーアカウントを使って長年隠蔽していた事件です。しかも銀行内部の検査でも発見できず、事件が明るみになったのは本人の告白によってでした。当初、告白を聞いた取締役たちがまじめに正面から取り組まなかった結果、大和銀行は米国全面撤退を余儀なくされました。担当取締役の任務懈怠の責任を認め、監視義務違反を認定したが、他の取締役の責任は否定したという事例です。
内部統制構築義務の判例② ダスキンの株主代表訴訟事件
池永 次に、ダスキンの株主代表訴訟事件があります。ご記憶の方もいらっしゃると思いますが、未認可の添加物を含んだ肉まんがダスキンの子会社を通じて販売されてしまっていたことが発覚しました。これを知っていた取締役が内規で定められている取締役会の報告を行わないで、さらに違法に会社の資金を捻出して、その事件を知った下請け会社の社長の口封じにお金を使ったという事案です。口封じしたことに関する内部統制構築義務違反は認めませんでしたが、そもそも肉まんが販売されたことを公表しないことを取締役会が何となく決めてしまったこと、公表することによって回避可能であった損害を被らせたこと、そこに善管注意義務違反があったということで、巨額の賠償責任を認めました。この事件では、監査役をやっていた弁護士に対しても責任が認められ、後に和解で解決するということを行っています。
公表するリスクと公表しないことによるリスクを判断する上では経営判断の原則が適用されます。経営判断原則は二つの要件からできています。まず経営判断をする上では、正当に状況の事実認識をしなければなりません。それには、事実がきっちり認識できるだけの情報を十分吸い上げているかどうか、ここに不注意がないかということが第1点目になります。第2点目は、そういった情報をもとに経営判断をする上で、その判断の過程と内容が著しく不合理でないかどうか、これが第2点目の要件になりまして、この二つの要件が満たされていれば、経営判断として内部統制構築をしたことに対して法は介入しない、つまり善管注意義務違反は認めないという理屈です。ダスキン事件でも、結局、公表することによるリスクと公表しないことによるリスクをしっかり検討していなかったため、アウトになりました。
内部統制構築義務の判例③ ヤクルト事件
池永 そして、ヤクルト事件がありました。これもデリバティブ取引で、当時、巨額損失を出した元副社長の行為をチェックできるリスク管理体制がなかった、ということで代表訴訟が起きました。これもそのリスクの隠蔽の仕方と、それから「代表取締役というのは、さまざまなことに取り組んでいるから、具体的な事項について業務担当取締役に対して委任した事項については、適切な報告を受けているかぎりにおいて特におかしいといえるような状況がないかぎりは、これについてさらに調査しなかったとしても注意義務違反はない」と判断したわけです。
内部統制構築義務の判例④ 日本システム技術事件
池永 最後に日本システム技術事件があります。これが最高裁として初めてまとめて判断した事例になりました。ここまでの流れを踏襲した判例になっています。
親会社取締役の責任の判例① 野村証券事件
池永 もう一つの流れとして子会社管理について親会社取締役の責任に関する判例がありますが、非常に事例は少ないです。例えば「野村証券事件」は、「親会社の取締役は、子会社の管理について原則的にいつも注意義務を払っていなければならないものではない」という判例を地裁が示しました。この判例が一人歩きをしているという批判もあります。
親会社取締役の責任の判例② 福岡魚市場事件
池永 最近、「福岡魚市場事件」の最高裁判決が出ました。複雑な内容を要約してみましょう。グルグル回し取引という、一種の循環取引によって不良在庫を抱えて経営破たんした子会社がありました。その親会社が、その子会社に対して不正融資を行って、融資相当額の損害が発生したことで代表訴訟が起こりました。親会社の取締役が子会社の取締役(非常勤)で、不良在庫が多いことを理由に調査委員会まで立ち上げた事情を知っていました。この事例に対して裁判所は、「不良在庫が多いことを知っていて調査委員会まで立ち上げたのだから、グルグル回し取引を中止させるべきだった」と、善管注意義務違反を認定しました。したがって、「そのあとの貸付自体の行為についての善管注意義務違反を認定するまでもなく、そこまで認識していたのだから、これは損害賠償義務がある」と判断をしたわけです。
この事例は具体的な事実関係に応じて善管注意義務違反を認定したもので、親会社の取締役会が子会社の内部統制構築について具体的にどんな義務を負っているかに踏み込んだ判断ではありません。しかし、これ以外に、そこまで判断した判例は、今まで出ていませんでした。
しかしながら、今般の会社法改正で、企業集団の業務の適正を確保するための体制に関する取締役会決議が制度化されれば、将来現れてくる変化が注目されます。現行会社法では、単体の内部統制構築に関する方針決議をやらなければならないことになっていて、立法担当者は「決議をすればいいのであって、極端な話、何も構築しないという決議でも違法ではない」という、意味不明の解説をしています。これについては私も大きな違和感を持ち続けています。学者の中には「それはおかしいだろう」と言う人もいます。しかし、立法担当者の話からすると、「これは方針決議だけだから企業集団と改正があったとしても影響を及ぼすものではない」という説明があり得るのです。
ただし、会社法改正の議論の中では、「多重代表訴訟の中で現行法上、親会社取締役が子会社またはその取締役の職務執行を管理監督する責任を負っているかどうかは明確でない」という指摘があり、「明文化すべきだ」という議論がありました。その議論は、経済界とか経産省が反対して潰れました。その代わりに、先ほどご紹介した「企業集団の業務の適正を確保するための体制に関する取締役会決議」が盛り込まれていったという具体的な経過があります。
企業集団の業務の適正を確保するための体制に関する取締役会決議の規定化については、「現行法の義務を超えない範囲で法律に明文を設ける」という説明がされていますが、一方で法制審の中の議論では、「親会社取締役は特段の事情がないかぎり、子会社の監督責任を負わないという解釈(先ほどの東京地裁のような判例)はもう支持されない」とか「監督義務を明確化すべきだ」という発言が有力な会社法学者から出ています。そういう中で、この制度が施行される流れにあり、子会社不正がかつてないほどにハイライトされているときに、「親会社の取締役は原則監督義務はない」という楽観的解釈が時代の支持を得るとは、私は個人的にはどうしても思えないわけで、子会社の監督に対する親会社の取締役の責任は厳格化していく流れにあると考えています。

業務執行と取締役の分離
森本 子会社に関して情報収集に基づく事実認識や判断が著しく合理性に欠けているというチェックに関して、取締役会が業務執行も実質的に担当しているケースが多くなっています。そのため、取締役の相互監視はあるものの、監督と執行が未分離なところも多いと思います。会社法上、内部統制の構築義務を問題にするとき、監督と執行の分離状況はどんな捉え方をされるのでしょうか。
池永 会社法上は厳格な分離が要求されていません。「各業務執行の状況を取締役会にどう報告させて、どう評価していくかのプロセスが適切になされているか」という見方が、裁判例でも非常に増えてきていると言えると思います。
森本 NSK様では非業務執行取締役から構成される監査委員会を設けられていますが、榎本様、実情はいかがでございますか。
榎本 NSKは委員会設置会社で取締役会に2名の社外取締役と1名の非執行社内取締役で構成される監査委員会を設置しています。
森本 監査委員会などの委員になる方は執行から外れるということですね。ありがとうございます。藤田様は、ガバナンスの観点から、この業務執行と取締役の分離に関してどう認識していらっしゃいますか。
藤田 私は経営の現場で執行の社内取締役を経験し、現在は独立の社外取締役をやっております。社外取締役は、当然、非執行です。会社法の建てつけでは、日本の取締役は二面性を持ちます。執行すると同時にその他の取締役の監督もするという仕組みになっています。欧米では、ほぼ執行と監督は完全に分離されていて、執行と取締役を兼務しているのはCEOぐらいというケースが多い。その他の取締役メンバーはすべて非執行で社外取締役という仕組みであるのはご承知のとおりです。こうした欧米と日本のガバナンス観点の違いによって、特に海外の機関投資家から、執行と監督の分離をもっと行うべきだという声が非常に強いです。NSKさんは、日本では非常に少ない委員会設置型です。委員会設置型のコーポレートガバナンスは、執行について取締役会は執行役側に基本的に経営執行権限を委譲する仕組みになっています。そして、執行の監督は、委員会が内部統制システムを通じて行うのがこの制度の建てつけです。
しかし、現実に委員会設置型において執行側の執行役会(例えば、経営会議)と、取締役会の審議の中身が本当に分離されているのでしょうか。多少疑問があります。監査役会設置型の取締役会は、今は執行的な案件を取締役会で決議をしているというケースが多い。委員会型は、本来それを執行役会(経営会議)に全部委譲して、内部統制システム等を通じてチェックしているはずです。しかし、現実には、取締役会の付議事項に執行的な案件があるのではないかという気もします。委員会型を採用しておられる日本の会社で、執行的な案件はすべて執行役会に渡し、取締役会では極力審議しないという会社があることも承知しております。ただ、経営の現場におりまして、今はそのあたりが両方とも十分でないのが一般的な現状であろうかと感じております。しかし、分離を進めていくことが、日本のガバナンスの次の課題の一つであろうと思います。
森本 三田様、いかがでしょうか。
三田 私は2年前に花王を卒業しましたが、卒業時の肩書きは、「取締役執行役員 会計財務部門統括」と、肩書きだけ見れば取締役と執行役とが分離せず一つの形になっていたわけです。私だけではなく、社内取締役は全員が執行役員を兼任していて、取締役会、執行役員会、経営会議で発言する時、どの立場で発言しているかを、常に自分自身も確認していた記憶があります。花王では2年に1回、取締役同士で各取締役を評価し、自分の直接の管轄部門メンバーにも評価される「360度評価」を実施していました。二十数項目の評価項目がありましたが、私自身の各評価項目の評価結果やフリーコメントなどを読むと、自分が取締役の立場で発言していたにもかかわらず、そうは思われていなかった、というようなことは往々にして感じていました。そこで私は、「取締役と執行役員の役割の違いは明らかにあるということを、今の役員の皆さん方が十分認識できるよう研修会をやってはどうでしょうか」と提案し、何回か弁護士の先生をお招きして、先ほどのお話のような事例等を聞かせていただきながら、認識を改めていた覚えがあります。
森本 どうもありがとうございます。経営統治の内部統制構築義務については、引き続きさまざまな局面で議論させていただきたいと思います。

先進企業における経営統治への取り組み
――その① 経営統治と会計財務部門の役割
森本 次に「先進企業における経営統治への取り組み」について、具体的にお伺いしたいと思います。
まず、「経営統治と会計財務部門の役割」についてです。グループ全体の経営統治を高めるには、まずは正確で迅速な会計数値の収集が必要です。それなくしては連結決算もできないし、計算が遅れるとグループ全体の統治の意思決定もできません。非常に基本的かつ重要な部分です。三田様は、経理・財務部門の役割の広範な部分を、シェアードサービスセンターも含めて担当されておられましたが、その当たりはいかがでしょうか。
三田 花王の扱っている商品は、非常に幅広く、100円、200円のものから、もっと高額なものまでさまざまです。
また、グローバルに事業を展開していく時に、各国や各エリアの気候や風土などに合わせてローカライズさせていくものが、家庭用製品の中にはたくさんあります。一方で、ケミカル製品に関しては、品質と価格さえ合えばグローバルにモノを届ける事ができる。この様に家庭用製品とケミカル製品とでは、事業展開の方法が大きく異なっています。
花王は、創業以来120年以上にわたって事業継続をしてきましたが、この間にはいろいろ苦しい時代もありました。花王には“よきモノづくり”という言葉があります。このよきモノづくりを通じて“豊かな生活文化の実現”を事業活動の基本に据え、創業以来の経営の基本精神をまとめ上げたのが「花王ウェイ」です。花王ウェイには、抽象的な表現もありますが、やはりこれが事業を進めるうえでの土台になっています。
先ほども講演の中でSAPのお話をかなり申し上げましたけれども、SAPは、それは確かに形の上では標準化されて、効率化されて、あるいはコンプライアンスが効くなど、いい面ももちろんあります。けれども、やはりSAPでいくら会計システムを整えても、そこを破る人間が現れてはどうしようもありません。破られないようにするには、基本的には個々の社員の考え方、モチベーションのあり方に落ちてくるように思います。
したがいまして、最終的に残るのは、各社お持ちの企業の文化や風土をまとめた○○ウェイと言ったような部分ではないかと思います。これは国内だけではなくて、海外の社員も同じです。自社の考え方、会社としてやるべきこと、守るべきこと、あるいは事業として進める上では、この考え方だけは絶対守らなければならないというのが、コンプライアンスの根底にあると思います。
森本 どうもありがとうございます。最後は「花王ウェイ」ということで、企業の文化や風土、基盤になる規範的なものはとても大事だと思いますが、この海外展開を進められる中で、ヨーロッパ等で花王ウェイを理解してもらうご苦労は、どういうものがあるでしょうか。
三田 国内と同じです。研修などいろいろな機会を捉えて「こういうことなんだよ」と話をしていくとか、トップマネジメントが現地に行ったときや現地の皆さん方が来たときなど、ともかく繰り返し、繰り返し伝えていくことが必要だろうと思います。私自身も、会計・財務部門のメンバー百数十人の皆さん方に「会計・財務の花王ウェイとはこういうことだ」ということを、花王ウェイを部門に落とし込む研修を1日半ほどの時間をかけて何回か行いました。最初は言っていることが地に着いていないのですが、何度も何度も言い続け、繰り返し説明することで、自分自身も花王ウェイで言っていることが信念に変わっていく感じを味わいました。
花王ウェイの“よきモノづくり”は、生産現場の担当であればよく理解できると思います。しかし、「会計・財務部門の“よきモノづくり”って何なの?」と問いかけると、なかなか最初は理解してもらえないのですが、モノづくりを“サービスの提供”に置き換えると理解しやすくなります。「私たち会計・財務のお客様は誰かと考えたとき、そこの人たちが満足できるような情報やサービスを提供する。それが私たちにとっての、“よきモノづくり”ではないでしょうか」という話に落とし込んでいけるわけです。
森本 花王ウェイを、経理・財務の方々には経理・財務の担当業務を通じて具体的にどう実現するかに落とし込み、繰り返し情報共有し教育されてきたのですね。この三田様のお話は、先ほど榎本様のお話にあった、財務本部・地域本部のCFO・事業部門の管理部門の方と3極体制でのコミュニケーションと同じですね。
榎本 そうですね。三田様がおっしゃった、「経理・財務にとってのお客様」つまり、「情報提供する相手」に重要な情報などスピード感をもってお届けする、ということをさらに充実させるためにも、本社財務本部、地域本部の経理・財務部門、事業本部の管理部門が連携していくことが重要になるわけです。
森本 システム面での標準化や統一と同時に基本的なピープルマネジメントが必須ということですね。ありがとうございました。

決算期、会計ルールの統一
森本 グローバル経営では決算期は12月のほうがよいということは頭ではわかっているのですが、花王様が決算期を12月末に統一されるにあたってはご苦労もあったかと思います。意思決定はどのようになされたのでしょうか。
三田 10年ほど前には、「決算期の統一は、海外の会社を3月に変えるよりも、むしろ国内を変えたほうが、マンパワーの面でもコンセンサスを得ていく上でも楽だし、コスト面でも大差はない」という感触を個人的には持っていました。そういう中で、ある会議でマーケティングや販売の役員から次のような話が出ました。「例えばグローバルリテイーラーとの新製品や販売促進活動などの年間の取り組み計画の商談では、相手は1月~12月の暦年ベースで考えている。4月~3月の期間での計画では、グローバルに仕事をしていく上で期が分かれてしまうので、商談は非常にやりにくい」と。また業績評価の面においても、海外会社の業績を加えて自分が統括している範囲を連結で見るとき、やはり3カ月のズレは経営実態が見えにくく、その評価もしにくい。そんな中で、「むしろ1月~12月に国内の会社の決算期間を変えたほうがいい」という発言があったのです。決算期間の変更は株主総会の開催時期も変わりますので、株主総会運営の事務局をはじめ関係者にとっては大変なパワーが必要です。ですが、会議に出席していた社長もあまり反対もされなかった。経営層の中では、12月決算への移行にあまり抵抗がないと感じてホッとしました。この会議が、決算期を12月に統一する大きなキッカケになりました。
何かインフラとかを変えようとしたとき、海外の皆さんからは、「日本花王はどうするのだ」とか「日本花王が変わるべきだ」とかの意見が必ず出てきます。今回の場合は、「日本が変わるから海外の皆さん方も協力してください」というスタンスで対応してきましたので、コンセンサスを得る上でも非常にやりやすかったと思います。実務担当の皆さん方も、うまく着地できるようご努力してくださったと思います。
森本 そういう発想が花王ウェイなのでしょうね。資金管理についても、通常ですと縦割りの発想が強くなりがちだと思いますが、そのあたりの抵抗はありませんでしたか。
三田 そこは、海外会社の日本人の社長も欧米の社長も考え方は同じでした。「自分たちが稼いだお金は、やっぱり自分たちで使います」と。何年か前までは、「日本に配当で還流させても高率な配当課税で目減りしてしまう。だから海外で持っていたほうがいい」という考え方が強くありました。しかし、税制が改正され、包括利益の概念も入ってくる中で、為替換算調整による振れ幅を小さくするには、海外の留保利益を配当によって日本に還流させることも一つの方法である、との考え方を各社に示しました。そうして4~5年前位から、還流させた資金を国内外の設備投資の資金需要に充当させてきました。
森本 ありがとうございます。榎本さんのところも、財務本部で、かなり決算期の早期化、勘定科目とか会計基準の統一、レポーティングシステム導入、IFRSの努力検討等、着実に会計・財務としての機能を果たし、成果をあげていらっしゃいますね。
榎本 決算期については、日本の日本精工本社を変えるのではなく、3~4年かけて海外の会社を3月期に変えていきました。当時、私は連結決算の部長をしていましたので、海外法人を回って、各社の経理、監査法人と話すなどしてきましたが、やはり最後の難関は中国でした。皆さんご承知のとおり、中国の制度は1~12月です。東京へのレポーティングを4~3月とすることで、最終的には統一しましたが、中国独特の会計処理などがあるなか、制度と異なる会計期間とすることは他地域に比べてハードルが高かったです。
また、会計ルールや勘定科目の統一を実施してから1年経ちましたが、グループ会計処理規定の内容はまだ改善の余地が多くあり、2年目に入って新たな取り組みを始めています。勘定科目についても整理や統合が必要だと思っています。さらに月次報告なども含めたレポーティング、あるいは原価関係の標準化も、グローバルに取り組んでいる最中です。
森本 なるほど、どうもありがとうございます。
髙橋様のドンキホーテホールディングスは、ドンキホーテ(ディスカウント業態)を中心とされていますが、長崎屋(スーパー)や、ドイト(ホームセンター)も買収し、業態も多様化しています。流通業は、お客様に対する対応の柔軟性が求められる半面、グループ全体も統括する必要があります。まずは御社の概要からご説明願います。
髙橋 ドンキホーテホールディングスは、2013年12月に、純粋持株会社体制としてスタートしました。企業コンセプトは、「便利で、安くて、面白く、楽しくありたい」という考え方を持っております。すなわちコンビニエンスと、ディスカウントと、アミューズメントです。コンビニエンスとディスカウントの具現化が小売ビジネスの基本と私たちは考えていますが、何よりも注力しているのがアミューズメントです。つまり、仕事をするときは、ゲーム感覚で面白くありたい、楽しくありたい。自分たちが楽しくあれば、小売店にご来店いただくお客様も感動し、楽しんでいただけるだろう――そんな考え方のコンセプトです。
ドンキホーテは、現会長CEOである安田隆夫が1980年に設立。当初は卸売業を中心としており、小売ビジネスへの本格的な参入は1989(平成元)年です。この年が小売ビジネス展開の実質創業の年となりますが、その1989年以来、2013年の決算まで24年連続して増収、営業増益を果たしています。これは3500社以上ある日本の上場会社中、2番手のポジションになります。ちなみに1番手は同じ小売業のニトリホールディングさんです。
店舗ネットワークは、日本国内の未進出県は4県のみで、43の都道府県に271店舗(2014年6月現在)を展開。海外はアメリカのハワイ州に5店舗、カリフォルニア州に9店舗、計14店舗を展開しています。海外事業は一気に商圏とお客様を獲得すべく、現地企業をM&Aで獲得しました(2006年及び2013年)。まだ規模は小さくささやかな状況ですが、海外事業を進めています。
森本 髙橋様はさまざまな経験をされておられますね。
髙橋 私は1997年ドンキホーテに入社するまでの約20年間を、紳士服チェーンのAOKIホールディングスで過ごしてまいりました。入社当時は売上高16億円ほどの規模でしたが、以来約20年間、チェーンストア経営における、およそ想定できる(社長業以外の)職位はすべて経験してきました。その中で経理、財務関係にも携わりながら、この会社の上場と成長に立ち会いました。そして1997年、ドンキホーテ(現ドンキホーテホールディング)に入社してからは、経営管理・経営企画・財務部門を管掌しながら、IR・広報部門なども担当しております。
森本 成長は目を見張るものがあります。急成長期のご苦労がおありだったと思います。
急成長期企業が抱えた「会計納期」の苦悩
髙橋 私が入社した1997年、売上高100億に満たない会社が、17年間に60倍、2014年は約6,000億円の売上高を計上。利益に至っても70倍を果たすような成長ぶりです。小売業の世界で多店舗展開が軌道に乗り、急成長をする中での課題は、事業成長に対して人材と仕組みが常に追いつかないことにありました。慢性的な人手不足も深刻でした。当社は24時間営業する店舗もありますが、私も24時間体制で臨みました。何とか会社らしい体制づくりをと、経営管理部門を中心とした体制づくりに注力しながらも、課題は山積していました。仕組みはパッチワークだらけで、どこが完成形なのか分からない状態のまま、3年後、5年後のあるべき姿をイメージして企画、実行しましたが、完成したと思ったらまたすぐにレベルアップしなければならない状況が常に続いてきたように思います。
経理・財務の中で、私が最も頭を痛めたのは、「会計の納期が守られないリスク」でした。ドンキホーテは6月決算でしたが、買収した当時の長崎屋は4月決算でした。長崎屋は日本の総合スーパーで、いち早く上場した老舗企業でしたが、経理部門には業務に長けた方がほとんどおらず、実務を行うために店舗経理を行っていた方を抜擢せざるを得ないような状況で最初の決算を迎えました。ところが、最初の年のレポーティングになんと4カ月かかりました。連結決算の取りまとめはなんとか乗り切りましたが、大きな反省材料となりました。まず外部の専門家集団に入ってもらい、会計処理をきちんとする。そして補助簿なども含めた科目内容を精査して決算の早期化を図る。併せて人員体制の強化も進める。これらがきちんと軌道に乗るまでには、さらに半年から9カ月ほどかかりました。
その他、買収したそれぞれの会社の決算期を統一したり、会計ルールの統合を進め、経理規程も改訂したりして、あたり前のことをあたり前に行える体制にレベルアップさせながら、普及・運用を図る、といったステップを踏んできました。さらにこれらを発展させながら、2013年には事務管理部門を各会社から分離して、シェアードサービス会社をつくりました。シェアードサービス部門でも経営目標を明確にして、グループ全体のバックオフィス機能でありながらも数値責任を負う、という仕組みで現在走り出したところです。
森本 どうもありがとうございます。

先進企業における経営統治への取り組み
――その② 経営統治と統括権限の整理
森本 次に、最も面倒だとも言える「統括権限の整理」に入ります。花王様が、アジア展開など行われるとき、そのプロダクトの事業部の縦のラインと、経理・財務をはじめとする本社の機能部門、さらに地域や国での権限を、どう調整しながら拡大されてきたのでしょうか。
マトリックス経営と連結事業利益の最大化への流れ
三田 アジアでも欧米でも、例外はありますがそれぞれの会社の事業規模はそれほど大きくはありません。そういう中で、従来は個々の会社ごとの収益の拡大を図ってきましたが、海外売上高比率はまだ30%程度です。花王グループの総合力(技術、資金の面、その他のノウハウ等々の経営資源)を発揮し、海外展開をさらに加速させ、事業規模の拡大を考えると、個別の会社の売り上げや利益の最大化を図るだけでは限界がありました。このため、2006年頃からアジアの会社と日本花王との一体運営を開始しました。そこで一応の成果を得ましたので、これを欧米の会社に展開し、今はグローバルに運営しています。事業軸と機能軸とのマトリックス運営という形で、海外各社の利益の最大化というよりも、連結ベースでの売上・利益の最大化を図る事業運営の方向性を変化させています。各社のコンプライアンスをきちんと行うことは当然として、経営の方向性は、連結事業利益の最大化という方向に向かっています。
森本 SAPの導入企業は、事業軸、地域軸等に、切り口を変えて業績を取り出すのも非常に楽になるかと思うのですが、例えばあるタイの販売会社の責任というのは、どちらが決算をしめて業績責任を持つわけでしょうか。
髙橋 個社の決算をないがしろにしているわけではないので、やはり責任はあるわけです。ただし、交点にあるところの経理のスタッフの皆さん方は、個社の決算も行いつつ、連結の数字も日本に報告するという、2ボスのような体制で動いています。
森本 藤田さん、商社はビジネスユニットが多様で、進出国も多いのでかなり複雑と思いますが、マトリックス経営の要点をお話しいただけますか。
藤田 総合商社は海外のオペレーションが非常に大きいことは明らかです。その際、経営統括を縦割りでやるか地域別でやるかは、会社によって大きく異なります。典型的と言われているのが、私の理解が正しければ、縦割りの強い思想で経営管理をされている三菱商事さん、地域が決算責任を強く持つ三井物産さんです。この二つのどちらがいいかという議論が古くからあります。例えば縦割りが非常に強くなると、地域におけるビジネス機会を逸してしまう恐れがあります。現地法人や支店、あるいは事業会社が、自分の判断で政策を立てて業容を伸ばそうとするのではなく、すべてが縦で決まることになれば、モチベーションが落ちたり、事業機会を失ったりする側面があることは事実です。一方、地域をベースにして決算責任を持ってやった場合、それなりの強みはあります。しかし、グローバルな政策で統一的な考え方の中でやったほうがいいビジネスも明らかにあります。会社全体をどちらにするかは、それぞれの会社と、その発展段階によって変えていくのが現実の姿ではないかと思います。
私がいた伊藤忠商事は、伝統的には三井物産型で、要するに現地は決算責任を持っているという考え方でした。ところが97年、私が本社で経営企画を担当していたとき、ディビジョンカンパニー制を導入しました。このとき、グローバルな縦割りの色彩を非常に強くしたのです。それはそれでグローバルなオペレーションが向いているビジネスには非常にいいのですが、一方で地域のビジネス機会獲得に関してはマイナスの側面があるので、一概にどちらがいいとは言えないと思います。
ただし、マトリックスと一言で言っても、具体的に動かすときは決算責任の所在(帰属)や経営計画を誰が立てるのかなどが重要になります。権限がないのに責任だけ負わされるのでは、当然、モチベーションは大きく失われます。海外事業が色濃い会社は、特にこのマトリックスのさじ加減がむずかしい。100対0ではなく、それぞれのビジネスの態様によって、多少現地側のウェイトを強くするとか、このビジネスに関しては明らかにグローバル一本でやったほうがいいというように選択していくのが、現実的でしょう。
さらに、やはり全体最適の観点から、バランスシートとP/Lの構造は、本社がグリップすることが当然必要だと思います。先ほど花王さんのお話にもありましたが、海外側が自分のところで出た利益は自分のところに置いておきたいと言っても、ずっと置いておくわけにはいかないはずです。連結側のオペレーションの大きさにもよりますが、連結経営の仕組みは、単体が投資して連結子会社あるいは関連会社から出てくる連結利益によって、全体の連結利益をつくり上げています。一方で配当は、単体のバランスシートから出すはずです。そして単体の配当原資は基本構造として二つあります。一つは単体のオペレーションからの利益を根源とする利益剰余金、もう一つは単体が投資している連結会社からの配当です。連結経営では単体が連結会社に投資をしているわけです。現地の利益を配当でとってこなければ、いつまで経っても単体側の配当原資はつくれません。本社がグリップする際、さまざまなリスクマネジメントや税務マネジメントが必要ですが、本質はそういうことだと思います。
森本 たしかにカントリーリスク、事業リスクなど全く異なるわけですから、グループ全体で統治して、業績を向上させるには、効率の最適を追求され過ぎてもと困る部分はございますね。榎本さん、この点いかがでしょうか。
榎本 内部統制の視点では、コーポレート経営本部が、取締役会が定めた内部統制の基本方針に基づいて、内部統制システムやリスク管理体制を整備する組織として、グループ全般に、内在するリスクを洗い出して分析評価を行い、取締役会に報告しています。具体的にはコンプライアンスや財務報告等のリスク管理も含まれています。
森本 横軸の機能面の管理ですね。どうもありがとうございました。

先進企業における経営統治への取り組み
――その③ 経営統治と本部要員の配置
森本 三つ目の、「経営統治と本部要員の配置」に移りたいと思います。例えば花王様の場合、会計・財務部門がコントローラー機能を強く持っていらっしゃって、単に過去数値の集計ではなくて、事業計画に実績値を近づけていくためのコントローラー機能も高めていらっしゃると思います。グローバル展開していくと、やはり経理・財務部門の人材を各国の拠点に配置していくといった動きも出てきます。そのとき、アジアは別として、欧州に配置するとマネージャーなのか、トレーニーなのかはっきりしないというケースを多々見てきました。ジョブディスクリプションがはっきりしない人を送り込むと、現地で円滑にいかないというケースもあります。そのあたり三田様いかがでしょうか。
グローバルなコミュニケーションの在り方
三田 花王の場合、海外に駐在している経理人材は大変少なくて、8名程度です。その内4名が中国で、あとは台湾とマレーシアに1名ずつで、ご質問の欧米には、アメリカに1名、スペインに1名です。欧米駐在の経理人材のうち、アメリカは入社して3年目ぐらいの若い人を、子会社にトレーニーとして2年間派遣しています。この間に経理実務やアメリカでの仕事のやり方を覚えることを目的として継続しています。
また、スペインに1名コントローラーという立場で派遣しています。彼ははっきりしたメンバーを抱えていませんが、組織図の中に「コントローラー」として位置づけていないと、現地の部長たちと直接話もできません。日本では若い人でもほかの部門の部長と話しをしても普通のことですが、スペインでは「なんでお前は俺のメンバーじゃないのに、俺のところに聞きに来るのか?」と言われるケースもあります。ですから、しっかりした立場と明確なミッションを与えています。欧米の場合、そうした体制を整えなければ、駐在させても仕事が思い切ってできないことがあると思います。
森本 現地に出されている駐在員の数が、思いのほか少ないように思いますが、コントローラー機能を発揮されるときに、会計・財務部門で各グローバル会議のようなコミュニケーションの場はどのような形で運営しておられますか。
三田 会計・財務主催のものは、欧米とアジアで年に2回ほど開催しています。それ以外に、予算の時期、下期の予算を見直すタイミングで、個々の会社の皆さんが日本に出張で来られますので、そういう機会を捉えて、現在の課題を共有していく体制を整えています。
森本 派遣と定例会議の両面ですね。ありがとうございました。NSK様では、外国人の方がボスにいらっしゃるということで、逆にグローバルが日本に還流しているような感じがいたします。榎本様、そのあたりの苦労話をお聞かせいただけますか。
榎本 コミュニケーションが難しいですね(笑)。私も長く一緒に仕事をしていますが、少なくとも彼との間には明らかに特に言語での問題はないのですが、問題解決へのアプローチが異なる場合があり、相互理解が難しいときがあります。外国人が日本に駐在して我々と働くという意味を考え、あるいは経理財務部門のグローバルな標準化を進めることや本社財務本部のグローバルなグリップ力強化などをお互いに共有しながら仕事を進めています。駐在員については、各拠点でそれぞれ会社発展の段階に応じてその役割は異なります。経理人材については、欧米では日本人が本社とのリエゾン的役割を果たすことが多く、一方、アジアでは日本人の駐在員がライン長や実務ラインに入って仕事を行うケースがありますが、同じアジアでもその関わり方には、地域や会社で濃淡があります。
森本 本部体制と併せて駐在面も重視されていますね。ありがとうございました。髙橋様はホールディングスのほうから財務・経理関係の方々を送り込むようなことはされていますか。
髙橋 私どもの場合は、企業買収して子会社数が増えた初期の段階から、それぞれの会社の経理業務を、本体(現在はホールディングス)に取り込む形を志向しておりました。例えば総合スーパーの長崎屋の場合は経理部門がありましたが、別組織で事務センターがありました。さらに長崎屋は、個店経営、つまり店舗ごとに経理業務を完結させて、そこで出た試算表を長崎屋の本部で集計・集約をし、その一部を本社のそばにある事務センターでサポートする、という仕組みを取っていました。私どもは階層を経たり、人の介在が多くなるごとに無駄やロスが発生するという考え方の下、生産性を上げて効率改善するために、買収した翌年にはドンキホーテ本体の経理部門に、長崎屋やホームセンターのドイトの経理部門のスタッフを、出向・異動させて、集中管理する仕組みをとりました。
一方で、海外事業は始めたばかりで現在14店舗しかありませんが、実はこれも非常に複雑な問題がありました。当初は2006年に、ダイエーのハワイにおける子会社を買収し、グループ化しました。次いで2013年にはマルカイコーポレーションを買収しました。この会社はハワイに2拠点、カリフォルニア、ロサンゼルスを中心に11拠点の店舗ネットワークを有しています。このマルカイが曲者でした。ハワイとカリフォルニアで行っている会計・経理がまったく違う仕組みで、勘定科目も異なるほどでした。マルカイの本部機能はハワイが持っていましたが、ハワイのCPA(会計監査人)がカリフォルニアに行くことがないということもありました。これらのことは正直申し上げて、デューデリジェンスのときには分かりませんでした。
私どもドンキホーテ本体からは、現地の経理業務を担当するスタッフ、マネージャーと面談、あるいは一緒に業務を行いながら、当社の監査法人に現地に行ってもらって、米国における監査人との連携を図りながら、まず棚卸をきちんとさせバランスシートを確定させるところからスタートしました。距離もありますし、言葉も十分通じないコミュニケーションの不自由さは感じておりますが、その距離を直接会話することで、あるいは直接行動することで、一つの方向性を見出て、それに向けてスタートをきったところです。
森本 やはり、M&Aでは想定外の対応が必要になります。どうもありがとうございました。
先進企業における経営統治への取り組み
――その④ 経営統治とコンプライアンスの強化
森本 次は「経営統治とコンプライアンスの強化」です。これも非常に大きな要素が出てまいります。メーカー系では、品質管理や安全基準などさまざまな規制を受けますが、非常に問題になるのは営業面ではないかと思います。業績追求とコンプライアンスの両立を図らなければならないためです。各国の規制改編の最新情報を把握するだけでも大変な上、各拠点での業務実態もつかむ必要があります。営業面は業務がどんどん広がっていきますから、本部が遠隔操作で全体を把握し、チェックするにも限界があろうかと思います。池永先生、このあたり、いかがでしょうか。
池永 今までのお話を非常に興味深くうかがっていまして、例えば統括権限の話や本部要員の配置の問題などは、広い意味でいえば取締役が社内資源について最適な配分ができているかという問題につながりますから、これも会社法の面でみれば法務の問題ではあります。
経営を行っていく上では、さまざまな状況に応じてさまざまな組織形態を考えていかなければなりません。藤田さんのお話の中に、ビジネスによって柔軟な組織形態を考える必要があるというお話がありましが、まさにそれが経営です。その中で取締役の善管注意義務や経営判断の原則は、一つの制度設計のツールという考え方で利用して設計に取り組む必要があると思います。
日本企業は財務報告の信頼性については、内部統制を強化してきた歴史がある半面、法務の点では若干の不安があるというのが正直な気持ちではあります。もちろん違法行為によるリスク減少への対応は、どの企業もかなり認識していると思います。問題は具体的にどうなのかという話です。独禁法違反や海外公務員に対する贈収賄の摘発事例が非常に増えていることからも、こういった問題に対する教育、モニタリング、問題発生時に専門的な法務的ガイダンスができる部員を、現地に置く必要性があることは間違いありません。つまり現地における対応力を向上させる必要性があるということです。
他方、法制の違いによって起こってくる不祥事は、本社にインパクトを生じますから、本社の法務部でもグリップを利かせなければなりません。ところが、現在の日本企業の現状を見ると、本社と現地双方で法務コンプライアンス機能を十分利かせることに成功している企業は、それほど多くはないように思います。どうしても現地は現地に任せっきりの会社が多いのではないでしょうか。その中でマネジメントは、リスクベースで限られたリソースをいかに有効に活用するかを法務の観点で考えることが必要になると思います。例えば、連結ベースで売上の8割、9割を自動車メーカーに依拠している部品メーカーでは、次期モデルの失注につながるような事態は最大の経営リスクです。法務的な観点で、そうしたリスクを防止する最適な体制を考えると、品質に問題が出たときの対応、リコールの問題などが主眼になってくると思います。そうした点に重点を置いて人材配備を考え、法務コンプライアンス機能の体制を考えていくというのがリスクベースのアプローチといえます。
各事業会社様の経営の実態によっているため、一律のスタンダードがあるわけではありません。しかも法務コンプライアンスの人材は、残念ながら非常に限定されています。現在、企業内弁護士が徐々に増えて、最近は900人に迫る勢いですが、まだまだ発展途上です。限られた法務人材をうまく配分していくには、経営の目が不可欠です。法務情報だけで配置するのではなく、連結ベースの経営を考え、何が最適かを考えていく。それが議論の筋になるのではないかと考えております。
法人格を超えて
森本 たしかに連結ベースの経営を考えれば、法人格を超えて、リスクマネジメントだけでなく、資金管理、取引の移転価格なども含めて、本部から適切にコンプライアンスの要員を送り込むなど、体制づくりが必要になってきますね。
池永 まさにそのとおりです。例えばアジアの統括会社をつくる場合には、経営上、重要なビジネスがそこにあるわけです。法務コンプライアンスについても、そういう考え方をとっていかなければ、おそらくリスク対応として十分でなくなるという側面は否定できないと思います。
森本 ありがとうございます。藤田さん、コンプライアンスについてはいかがでしょうか。
藤田 コーポレートガバナンスの設計や内部統制の仕組みなど、企業にはさまざまな課題があります。それらを総合する重要な観点として、私は「企業文化」と「価値観」を挙げました。コンプライアンスについて言えば、「不正を許さない」という企業文化、価値観がないと、自分たちの会社共同体を守るために、「多少の問題はかまわない」と思ってしまう面があると思います。規則や法律、仕組みは非常に大事ですが、特に今コンプライアンス問題の根底にある重要な問題は、企業文化や価値観であることをあえて申し上げておきたいと思います。企業文化や価値観は、社内で常に共有していかなければなりません。それには、やはりトップが常にメッセージし続けることが極めて大事です。
今はドメスティックだけでやっておられる日本企業もいらっしゃいます。しかし、日本の人口構造や経済構造から考えても、好むと好まざるとにかかわらず、海外でのオペレーション、海外との関係が増えていくと私は思います。そのとき、日本の中での法律の知識とかコンプライアンス対応に加えて、グローバルベースでのそのような情報をいかに把握をしておくか。たぶんそれは各地からの情報を収集しながら、本社がグリップするということでありましょうが、例えばFCPA(米国海外不正支払い腐敗行為防止法)の話が先ほど出てまいりました。また、UKのAnti-Bribery lawの話も出てまいりました。独禁法の話ももちろんございます。あるいはtransfer priceの話も。こういう、要するに基本的な情報というのを、オペレーションがグローバル化すればするほどどこかが握っていないと、企業はどこかで大きなリスクを持つということであります。一度このリスクが顕在化すると、実は半端な金額ではないわけでありまして、企業があっという間に潰れるリスクだってございます。
海外も含めたコンプライアンスに関連した情報の把握は極めて重要です。それに対応するためにも、私はグローバルな人材の教育、あるいはローテーションが義務であろうと思えてなりません。法務人材の話がありましたが、財務・経理においてもそういう人材を養成/確保する必要があります。リスクマネジメントしかりです。それを日本人の社員、ローカルスタッフという位置づけではなく、企業全体の人材として把握するアプローチが今後ますます大事になると、私はあえて申し上げておきたい。そうしますと、例えば法務も経理も、日本の本部にいる人だけを見るのではなく、ロンドン、シンガポール、中国に置いている人がどのレベルなのか、人材のレーティング(資格/能力尺度)をグローバルベースでつくり上げておく必要があるでしょう。グローバルな人事管理と、特に専門要員のレーティング、それを育てる仕組みをぜひそれぞれの会社で考え、かつサクセッションプランを持っておいていただきたいと思います。それぞれのポジションについて、その人が何らかの理由で会社を辞めたり、病気になったりした場合も、滞りなく運営できる仕組みになっているかも見ておくのが会社経営であろうと思います。
商社は海外オペレーションの経験が比較的長いので、それなりの蓄積/対応力はあると思います。それでも不正や不祥事が起きるのが現実です。それに対する対策は、最初に申し上げたようなことをやっておく必要があると、重ねて申し上げておきたいと思います。

普遍的な企業価値観の重要性
森本 どうもありがとうございます。たしかにビジネスモデルもどんどん変わっていきますし、コンプライアンスの話は、結局、企業倫理の話やリスクマネジメントの話と境界があるようでないようなところがございます。
私もご支援させていただいている大手エレクトロニクスメーカーの場合、反トラスト法、独占禁止法により、テレビ、冷蔵庫、ファクシミリなどにおいて、台湾、韓国、中国のメーカーに攻められました。一方ではコモディティ化した電化製品は、常に価格競争に巻き込まれて、談合しなければ利益が確保できないという構造的にリスクを高めるような環境があることを、マネジメントもはっきりと意識しておくことも必要でしょう。そのときどうするかという企業倫理を、経営者は直接指導してあげなければなりません。事業部にしてみると、皆さん頑張ろうと思ってやっているわけです。放っておくとそうなってしまい、同じことが繰り返されるのだろうと思います。
池永先生、繰り返しの質問になりますが、そういう点はいかがでございますか。
池永 まさにビジネスが置かれている環境が経営者の行動をドライブするというお話だと思うのですね。だからこそ、まさに藤田さんがおっしゃられた経営陣の企業文化、「われわれの価値はこういうものだ」というのを、トップが全世界の従業員に対してはっきり発信することが非常に重要になってくると思います。
ご指摘のような事例では、談合、あるいは談合まで行かなくても情報交換でもしなければやっていられない世界なのだという感覚が現場にあると思います。その部門の従業員は収益を上げるのに一生懸命努力しているわけで、悪いという意識がありつつもやってしまうこともあり得ます。それをトップの経営陣がリスクとして認識して、「そういうことはやっちゃいけない。そういう場合には、われわれはこういうふうにやっていくんだ」というものを発信することがやはりコンプライアンスの根本にあるということで、藤田さんに大変重要な指摘をしていただいたと思っております。
森本 どうもありがとうございます。なかなか何が談合に当たるかとか、それ自身も現場で徹底しにくいところもあろうかと思いますが。
池永 そうですね。ただ、情報交換しただけで、米国ではコンスピラシー(共謀)の理論で、現実に非常にたくさんのメーカーが民事制裁金を課されています。独禁法についていえば、恐ろしいのは、それだけですまないということです。現在も日本のビジネスエグゼクティブで、連邦刑務所に服役している方が30人近くいます。加えて仕入先の自動車メーカーからの損害賠償が、次に襲ってきます。この連鎖が始まると、どこまで行っても対応が終わらないし、弁護士費用も、莫大になります。だから、そういうことを起こさないためには、そうしたリスクがあることを認識して、まずはトップが明確な行動規範、バリューを示すというところに帰らなければ、本当に止まらないでしょう。
森本 最近では、リニエンシーを行使しなかったという理由で、株主代表訴訟の事件が起こっているような企業もあります。それが日常化していく可能性はあるということでしょうか。
池永 あると思います。さらに、談合やカルテルにかかわっても、リニエンシーで駆け込めば、その企業自体はペナルティを受けませんが、リニエンシーを申請したという情報は確実に流れますから、結局、申仕入れ先の自動車メーカーから非常に厳しい要求がされることが起こりえます。課徴金や刑事告発は免除されても、談合やカルテルにかかわったこと自体がビジネス全体に影響を及ぼす可能性も十分ありますから、重々注意が必要です。
森本 どうもありがとうございます。榎本様のほうでも、最近、コンプライアンス体制の抜本的な強化に取り組んでいらっしゃるようですけれども、そのあたりをお話しいただけますでしょうか。
榎本 独禁法の話がありましたが、3年前にNSKも独禁法違反がありました。以来企業風土の改革も含めて、コンプライアンス強化を強く推進しています。具体的にはコンプライアンス研修や、従業員へのガイドブック配布などを行っていますが、やはりいちばん重要なのは、まさに藤田理事長がおっしゃった、トップからのメッセージであると認識しています。この間、トップからは、「コンプライアンスがNO1プライオリティ」というメッセージが繰り返され、そういう意識が醸成されてきていると感じています。
森本 ありがとうございます。最近、企業倫理の浸透の方法も、だんだんリアルになってきました。いろいろ教育用のビデオもリアル感の強いもので教育なさっているところもございますね。以上でコンプライアンスについては本質に迫れたように思います。
先進企業における経営統治への取り組み
――その⑤ 経営統治と合併買収
森本 次は「経営統治と合併買収」の問題です。最も経営統治が大きくクローズアップされる部分かと思います。統合を図るにもさまざまなレベルがあります。事業計画のレベル、あるいは組織や人事、業務、さらにプロセス、最後にシステムまで。どこまで標準化や統一化するか。そのレベル感はそれぞれの業態や事業規模によって柔軟に判断する必要があろうかと思います。花王様も買収関係をたくさん手がけてこれらましたが、三田様、そのへんはいかがでしょうか。
ブランド価値を維持・拡大させるために
三田 カネボウ化粧品の例をお話しします。カネボウ化粧品には四千数百億円投資しましたが、投資額が大きくなったのは、カネボウブランドから生まれてくるのれんと知財権等の無形資産をしっかりと評価したことによります。このため、このブランドが毀損しないようにマーケティングや販売、企業文化などを議論する時には非常に注意し、またカネボウ化粧品の自主性を尊重しました。
さらに、企業価値を高めるためにデューデリジェンスを通じて発見したいくつかのポイントを、花王のインフラやノウハウなどを使ってシナジーを発掘させることに、数年間は注力しました。講演でお話をしたITシステムの利用などで効果は出てきました。しかし、それを進める上では、頭の中ではわかっていても、心情として受け入れがたいとか、あるいは新しいシステムに変えることで自分たちの仕事が変わってしまうとか、なくなってしまうという不安が随分あったように思います。「効率化」という言葉自体が、ある面ではリストラにつながると考える方もおられましたので、基本的には効率化という言葉はあまり使わず、「仕事のやり方を変えることによって創出されるマンパワーは、新しい業務に振り向けていきましょう」という言い方をしながら、カネボウ化粧品の皆さんと一緒になって取り組んできました。2013年に大変お騒がせした美白化粧品の白斑問題について、外から見ているかぎりでは情報がタイムリーに上に上がってこなかったところから発生したのではないかと思います。素早く対応していれば、これだけ大きな問題にはならなかったと思いますが、残念ながらスピード感が足りなかったのではないかと思います。1年や2年では、なかなか心の中まで一緒になれません。例えば、花王の持つインフラやノウハウを利用することによってカネボウ化粧品側でメリットを感じられることをいくつも積み上げていくことで、本当の意味でのグループ化が図れていくのだろうと思います。カネボウ化粧品が花王グループ化してからしばらくの間は投資家の皆様方からは、「なんでリストラしないのですか」という質問をしばしば受けました。「そういうことをすることでブランド価値が毀損してしまう可能性がある。カネボウ化粧品の持つ企業文化や自主性を大切にする」という説明を繰り返し説明することで理解を求めてきました。
ビジョンを語り続け共有化する
森本 支払業務や営業の取引事務に関して大連などを使ったオフショアのBPOは、どういう形で導入されたのでしょうか。
三田 支払やお取引関係の管理システムは、花王の方が整備されていることはカネボウ化粧品側も認識していましたので、花王のシステムで行う方向性を出す中で、内部牽制の充実やプロジェクト要員の創出を図るために、SSC化やオフショアでのBPO化を計画しましたが、やはり抵抗感はありました。計画を進める中で、自分たちの仕事のやり方が変わったり、業務そのものがBPO先に移管されたりしますので、「皆さんの仕事はこういうようなやり方に変わります」ということをはっきり明示しました。先ほど藤田理事長から、「トップが常にメッセージを発し続けることが大事です」というお話がありましたけれども、やはり各会社、各部門、あるいは各グループでも同じだと思います。リーダーたる人たちが将来のビジョン、つまり今やっていることに対して、「こういうふうに変わっていくので、これはこういうふうに行きましょう」、「何年かしたら、こういう像になります」ということを言い続けることによって将来像を理解していただく。メンバーの皆さんと一緒に取り組む中で、そうした進め方が大事だと感じました。
森本 どうもありがとうございます。NSK様は、少し古くなるかもしれませんがポーランドやイギリスの会社買収を手掛けられました。榎本様、そのときはいかがでしたか。
榎本 二十数年前、イギリスの老舗ベアリングメーカーを買収しました。買収後、現地のマネジメントにはかなりの自由度を持たせて、本社からはあまり介入せず事業運営を進めさせていました。しかし、その後、パフォーマンスが向上しないこともあって、リストラを繰り返しましたが、現在では一部の工場が再生されたほか、製品ブランドや販売網など無形の資産も活用しています。十数年前にポーランドの国営企業を買収した事例では、買収直後からNSKが現地マネジメントに参画しました。この企業はそれ以前にNSKから生産設備等を輸出していたので、技術がもともとNSK流であり、そのため生産・技術面などでは比較的早く融合できたのだと思います。ただし、経理・財務についていえば、欧州の仕組みの中に取り込むのに、相応の時間がかかりました。
従業員のモチベーションアップという課題
森本 ありがとうございます。髙橋様はいかがでしょうか。
髙橋 私どもは、1989年から2005年まではドンキホーテというディスカウントストアのみで国内事業を中心に拡大策を取ってきました。2006年からはM&Aという形で事業の新たなステージに入りました。このときにいくつかの悩みが生じました。文化、歴史、社風が、まったく異なる会社がグループに入ったということ、事務部門・管理部門の集約・統合も必要でした。ドンキホーテという会社は企業としては若く、「スピードこそがクオリティを変える」という信念の下で、常に前進し業績を拡大してまいりました。しかし被買収会社は、業績が振るわず民事再生という状況の会社もあったため、従業員のモチベーションを上げることが大きな課題であり、活性化策を繰り返してきました。
こうした過去のM&Aは、ドンキホーテという小売ビジネスの拡大策の一環であり、買収する会社の資産で最も活用したかったのは、店舗そのものの、出店立地、ロケーションでしたが、何よりも重要なものは人材。当初の段階から創造的破壊、あるいは事業の改革をテーマとして、それぞれの会社の従業員の方に浸透させるように努力してきました。
買収した会社のマネジメント体制や店舗営業の状態を見る期間であっても、「スピードそのものが経営のクオリティを上げる」という概念を各会社に浸透させるため、「この期限までにこの予算を(この経営目標を)達成しなければ、あなたはアウトですよ」というような信賞必罰を明確にするスタイルを持ち込み、それに応じた形で推進できたと思っています。
今申し上げたことは営業部門に限らず、財務・経理部門も同様です。納期の管理が私たちの課題であったということは再三申し上げておりますけれども、生産性の重要度を、それぞれの会社の人たちに認識してもらうために、権限と責任を明確にして、クオリティアップと少人数でもできる仕組みで意識改革をしてきたつもりです。具体的には人材をシャッフルしながら、組織の統合、集約を実施しました。業務の中で生産性が上がらない、つまり目標に達しきれなかった人たちは、財務・経理部門から店舗営業部門に配置転換しました。適材適所という面でも、全体のコストダウン、あるいは収益化に貢献できたと思っております。
森本 経営効率改善とモラル維持はM&Aの場合、特に難題ですね。どうもありがとうございました。

討議を踏まえた今後の日本企業の経営統治への取り組みの必要性
森本 最後に今までのお話を総括して、藤田様から今後の日本企業の課題、あるいは目指すべき方向という総括的なお話をお願いいたします。
藤田 冒頭で日本企業のコーポレートガバナンスの内面にある問題ということで、私なりの意見を申し上げました。日本という国は、コーポレートガバナンスという視点からいうと、残念ながら今まで後進国であったと思います。戦後の長い企業経営の歴史の中で、コーポレートガバナンスを改善していくようなプレッシャーがなかった。日本企業の独特の特徴は、もちろん良い面もあります。しかし、株主は経営にほとんどプレッシャーをかけませんでした。経済が上向きのときはそれでもよかった。しかし、そうでないとき、それが逆風になったわけです。
しかしながら、幸いにしていろいろな契機をドライバーにして、コーポレートガバナンスのさまざまな面での改革が進められています。ただし、何度も申し上げますが、形式にとらわれてはなりません。それぞれ会社を取り巻く環境や方向は、各社異なるはずです。画一的なコーポレートガバナンスは、むしろ排すべきでしょう。ぜひ、独自のガバナンスを設計して、最適なものをつくり運営していただきたいと思います。
持続的成長を目指すのはマネジメントの使命ですが、ガバナンスの観点からいえば、株主を含めたステークホルダーの利益も常にチェックしなければなりません。かつ、社外取締役の導入は必須だと思いますが、法律で入れるのは必ずしも賛成しません。ぜひ、会社が独自にその効用を理解し、設計していただきたいと思います。
花王さんは監査役会型であり、NSKさんは委員会型であり、ドンキホーテさんは独特のビジネスモデルで発展をしてこられた。まさに企業ごとに異なる環境に対応して独自に最適なスタイルをつくられています。繰り返しになりますが、日本はコーポレートガバナンス・コードを一日も早くつくるべきです。ただし、それはソフトロー即ち強制的なものではなくて、ベストプラクティスを示して、comply or explainを日本でも行っていただきたいということを申し上げて、私からの意見とさせていただきます。
森本 ありがとうございました。すべての企業がコーポレートガバナンス経営統治という山に登らなければなりませんが、登る方法はいろいろあります。コーポレートガバナンスの確立を図る一方で、コンプライアンスやリスクマネジメントを高度化し、グループ全体の業績向上にそれぞれ取り組んでいく必要があるというお話でございますね。
本日は皆さま、どうもありがとうございました。
※本稿は、2014年5月22日開催の「グループ経営統治力の強化とその実践セミナー~改訂COSOフレームワークを活用したグループ経営統治力の強化と経営管理体制の見直し~」の講演内容を編集部にてまとめたものです。
2014年9月16日







