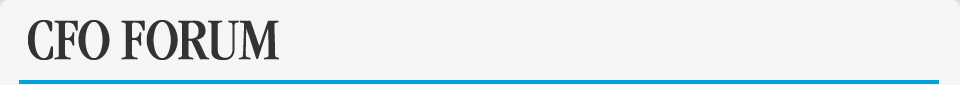
2017年2月15日
弁護士は喜んで成仏すべきか
森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
他人に業務を委任するとき、他人に広範囲な裁量を与え、事実上、身を任すような事態にならざるを得ない場合がある。典型的に、医師にかかるとき、弁護士に訴訟等の代理人を委任するとき、金融機関等に資産の運用管理を一任するときなどである。
このような特殊な委任を受けた医師、弁護士、金融機関等はフィデューシャリーと呼ばれ、他人からの信認、即ち、決して裏切ることのできない最高度の信頼を得たものとして、専らに顧客のために働く重い義務を負う。この義務をフィデューシャリー・デューティーと呼ぶのである。
この耳慣れない片仮名が脚光を浴びるようになったのは、金融庁の森信親長官の大胆な改革路線のなかで、金融機関が行う投資信託の販売と運用に関して、フィデューシャリー・デューティーの徹底を求めたことがきっかけである。
成仏理論
さて、実は、代表的なフィデューシャリーは弁護士である。その弁護士の世界で有名なものに、成仏理論がある。原典は、雑誌「法学教室」の2006年4月号の「巻頭言」として公表された「成仏」という異様な表題の短文である。筆者は、当時、東京大学教授であった高橋宏志氏だ。
この論考の背景には、司法制度改革がある。改革の一つの柱は、法曹人口の拡大だから、「成仏」は、「法律家が増え続けることになっているが、新人法律家の未来はどうなるであろうか」と書き出されていて、「暗い予想」として、「食べていけない新人法律家が一定数出ると予想するのである」としているのだ。
逆に、「明るい見通しもある」のだから、要は、「器量と努力次第でどちらにもなる」のであって、「食べていけるかどうかを法律家が考えるというのが間違っているのである」として、「何のために法律家を志したのか」と問い、成仏理論につながるのだ。以下、引用しよう。
「人々の役に立つ仕事をしていれば、法律家も飢え死にすることはないであろう。飢え死にさえしなければ、人間、まずはそれでよいのではないか。その上に人々から感謝されることがあるのであれば、人間、喜んで成仏できるというものであろう」
弁護士からの反発
改革の結果として、弁護士の数は増大したわけだが、社会の状況は大きく変わっていない以上、弁護士の仕事が並行して増大したという事実はなく、結局、現状では、「暗い予想」のほうが優勢なのである。そういうなかで、この成仏理論が怨嗟の的になるのも肯ける。
もっとも、おそらくは、成仏理論が批判される本当の理由は、東京大学教授という立派な身分保障のもとに発言されたことと、高橋宏志氏は、退官後も、中央大学教授、森・濱田松本法律事務所客員弁護士、東京大学名誉教授という輝かしい肩書を保持されていることであろう。こういう身分の方から、君らは成仏、といわれれば、感情的反発を覚えるのもやむを得ない。
しかし、成仏理論の根本的な問題性は、「人々の役に立つ仕事をしていれば、法律家も飢え死にすることはない」という前提にある。
この「飢え死にすることはない」という経済状態は、全体の論旨からして、かろうじて生計が成り立つ程度の所得しか得られないという意味に解するほかない。しかし、真に「人々の役に立つ仕事」をする限り、そこに社会的価値の創出があるわけだから、「飢え死にすることはない」どころか、実現した価値に応じた所得があってしかるべきである。それが経済の合理性である。
フィデューシャリー・デューティーと合理的報酬
フィデューシャリーは、専らに顧客のために働く義務を負うので、自己の利益を鑑みることはできず、理論を突き詰めれば、無償で働かなくてはならないことになる。しかし、それでは職業として成り立たないので、専らに顧客のために働くのに要する原価を基準に、合理的に算出された報酬を受け取ってよいものと理解されている。逆に、合理性を超える報酬は、フィデューシャリー・デューティー違反になるということだ。
金融庁は、金融機関のフィデューシャリー・デューティーについて、この点を問題にして、特に投資信託の販売手数料等の是正を強く求めているのだが、決して、とるなとか引き下げろといっているのではない。あくまでも、提供した役務を基準に報酬等の額を定めよといっているだけである。
金融機関として、フィデューシャリー・デューティーによって報酬が減って困るなどといっているものに、未来は全くない。逆に、顧客の視点に立ってより価値の高い仕事をすれば、提供した価値に応じて増収になると考えるべきだ。そこに、金融庁のいうフィデューシャリー・デューティーの本質があるのだ。
つまり、フィデューシャリー・デューティーのもと、顧客の視点と合理的報酬の考え方を徹底すれば、顧客に提供する価値の増大こそが経営課題となり、その結果として、顧客の利益も金融機関自身の利益も相互に矛盾対立することなく、増大するはずだということである。
ベストを尽くす義務
故に、成仏理論の第二項、「飢え死にさえしなければ、人間、まずはそれでよいのではないか」も間違っている。「飢え死にさえしなければ」程度では、人間、少しもよくはない。そのような境遇に甘んじてはいけない。そうではなくて、金融庁がいうようにベストプラクティスを追求しなくてはならない。
弁護士には、依頼人のためにベストを尽くして訴訟遂行する義務があり、医師には、ベストを尽くして患者の健康回復に努める義務があり、資産の運用管理を受任した金融機関には、ベストを尽くして投資収益をあげる義務がある。
では、逆に、職務遂行においてベストを尽くしても、「飢え死にさえしなければ」程度の所得にしかならないのかといえば、個々のフィデューシャリーにおいて、そのような不幸な人のあり得ることは否定できないが、フィデューシャリー業全体が存立し得る限り、あり得ないことである。なぜなら、もしそうなら、ベストを尽くしても社会的価値は増大しないということだから、それではそもそも業としての存立基盤がないはずだからである。
社会の役に立たないことにベストを尽くしても、意味はない。また、本人は「人々の役に立つ仕事」をしているつもりでも、社会的にみれば「人々の役に立つ仕事」ではない可能性がある。これでは、「飢え死にさえしなければ」程度も維持できないだろう。
成仏するのはいいことか
最後に、成仏理論の第三項、「人々から感謝されることがあるのであれば、人間、喜んで成仏できる」はどうか。「人々から感謝されることがあるのであれば」というのは、感謝されない場合を普通の事態としているようだが、そもそも真に「人々の役に立つ仕事」をして、感謝されないことはあり得ない。また、感謝されて、喜んで成仏するわけにはいかないし、その必要もない。
「私はどうか。不可(F)を付けまくる、役に立たない鬼教授と言われているようであるが、極楽浄土に成仏できることを私は心から願っている」──これが「成仏」の結びだが、その真意は不明である。
2017年2月15日






