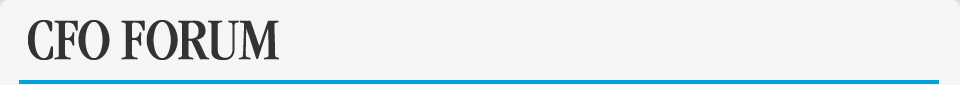
2016年5月16日
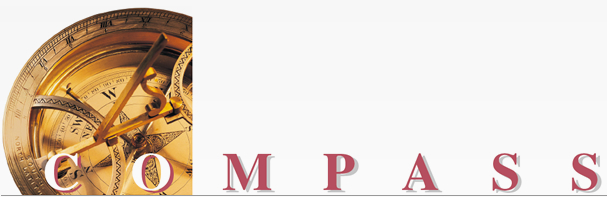
監査役等設置会社は「前進」か「後退」か
磯山 友幸
経済ジャーナリスト
元日本経済新聞記者
3月25日、東京証券取引所市場1部上場のオプトホールディング(以下オプト)の株主総会が開かれた。これまで大株主でCEO(最高経営責任者)の鉢嶺登氏が支配権を掌握し、毎年の株主総会は話題になることもなかったが、今回は違った。
同社株の約5%を保有する投資ファンドのRMBキャピタル(米国・シカゴ)が、会社側が総会にかけた提案に反対したからだ。RMBは富裕層などから資金を預かり長期投資を行っているファンドで、別会社から引き継いだファンドを通じて2012年頃からオプトに投資してきた。長期投資の安定株主とみられてきたファンドから反対を突きつけられたのである。
RMBが反対したのは監査等委員会設置会社への移行。2015年5月の会社法改正で導入された。それまでの会社法で規定されていた「委員会設置会社」は、社外取締役が過半を占める「指名委員会」と「報酬委員会」、「監査委員会」の3つを設置することが義務づけられていた。これが新制度では、「指名」と「報酬」の委員会は置かず、監査委員会だけを置くことができる。また、監査等委員会設置会社に設置すれば、それまで置いていた監査役は廃止することも可能だ。
昨年5月の新会社法では、社外取締役の実質的な義務づけが大きな話題になった。法文上は義務づけられていないが、社外取締役がいない場合、「置くことが相当でない理由」を株主総会で説明しなければならない。このため、多くの会社で社外取締役の導入の動きが加速した。
そんな中で急速に注目されたのが、監査等委員会設置会社だ。今年6月の株主総会シーズンまでに400を超す会社で導入される見通しになっている。
海外ファンドなど、コーポレートガバナンス(企業統治)の行方に強い関心を持っている投資家は、当初、監査等委員会設置会社は、世界に例のない日本型の監査役会設置会社からグローバルスタンダードである委員会設置会社へと日本企業が変わっていく「過渡期」だと見ていた。このため、導入に際しての議決権行使では、賛成票を投じてきた。
米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)など議決権行使助言会社も「賛成」するよう助言してきた。
ところが、監査等委員会設置会社に移行する会社が増えるにつれ、監査役を廃止するデメリットを強調する声が強まった。監査役制度はかつて「閑散役」などと揶揄され、機能しない制度の典型とみられてきた。一方で度重なる法改正によって監査役の機能強化が図られ、任期の延長などによる独立性の強化や監査役室の設置による常勤スタッフの強化、社外監査役の義務づけなどが進んできた。
これを廃止し、社外取締役からなる監査委員会で足りるとすれば、社外役員の総数はこれまでと変わらないうえ、常勤で監査に携わる役員が減り、スタッフもなくすことが可能になる。監査等委員会設置会社は、世界に類を見ない日本独特の制度になるのではないか、という見方が広がりつつある。
つまり、コーポレートガバナンスからみて、強化に向けた前進ではなく後退ではないか、という疑念が広まっているのだ。
それに真正面から疑問を呈したのがRMBだった。12月決算会社のオプトでひと足先に疑問を呈したというのだ。
オプトで運用しているポートフォリオ・マネジャーは、野村証券出身の細水政和氏。細水氏はこれまで何度も鉢嶺CEOに会い、積極的に「対話」を繰り返してきた。
オプトに対してRMBは、買収防衛策の廃止や大量に保有する自社株の消却を求めてきた。オプト側は買収防衛策の廃止は受け入れたものの、その後、監査等委員会設置会社への移行を打ち出し、これにRMB側が反発していた。
細水氏は「指名委員会と報酬委員会を置かない制度をなぜ導入するのか、米国人にも理解できない」と語る。放っておけば、「日本企業が雪崩を打って監査等委員会設置会社に移行し、世界には通用しないガラパゴス状態に陥りかねない」というのだ。
総会では結局、会社提案が承認されたが、反対票も19.79%に達した。今後、世界の機関投資家が日本の監査役等委員会設置会社に関心を持ち、それが本当に日本企業のガバナンス強化につながっているのかどうかを検証することになるだろう。
2016年5月16日






