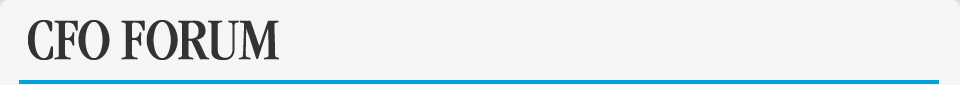
2016年1月15日
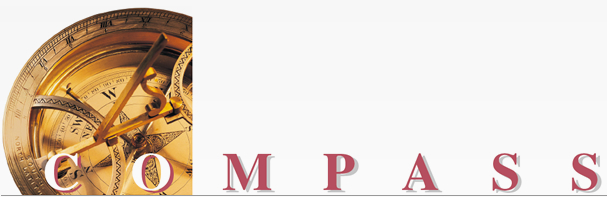
会計士は経営者の“味方”
磯山 友幸
経済ジャーナリスト
元日本経済新聞記者
「東芝が会計士の目をごまかすために行った偽装工作は凄まじい。(米国で巨額粉飾のうえ破綻した)エンロン並みですよ」
東芝を監査してきた新日本監査法人に近い会計士はそう語る。東芝は巨額の粉飾を会計士に悟られないよう、徹底的に会計士を“敵視”し、損失表面化を避けるための周到な説明資料を用意していたという。新日本の幹部も東芝との関係が「どんどん事務的になってきていた」と振り返るが、経営者と会計士の間で、本音の議論がまったく行われていなかったことを示している。
経営者にとって会計監査人、つまり会計士は、時として鬱陶しい存在だ。特に会社の決算を預かるCFO(最高財務責任者)にしてみれば、会社の実状を分かりもしない外部の人間が、会計ルールを振りかざして、細かいことに口出しをしてくる。「敬して遠ざけたい」存在に映ることがしばしばある。
かつては経営トップが新入社員だった頃から会社に出入りしていたような「大先生」が監査する会計士を束ねていて、社長も一目置いていた。ところが最近は、数年で交代する会計士が理屈だけを並べるようになった。資格を持った会計士より、百戦錬磨の経理社員の方が当然会社のことは分かっているし、はるかに実務知識も豊富だという意識の上での「逆転現象」が起きている。
「資格を持っているからと言って、何であんな若造の言うことを聞かなければいけないのか」
口にこそ出して言わないまでも、そう感じているCFOは少なからずいる。
民主党政権時代、会計士制度の見直し策として、「財務会計士」という資格を創設する案が浮上した。国会での成立まであと一歩に迫ったが、結局はとん挫した。企業で実務経験の長い社員に資格を与えるというものだったが、そんな案が経済団体から出てきた背景にも、企業経営者側の会計士に対する強い不満があった。
実務経験が乏しく自信がない会計士ほど、ルールを振りかざして居丈高になる。あたかも金融庁から派遣されてくる検査官のような会計士もいる。そうかと思えば、パソコンを眺めているだけで、役に立つアドバイスをほとんどせずに帰っていく会計士もいる。にもかかわらず報酬だけは数千万円、数億円と請求してくる。どうみても会計士の年収は経理部長をはるかに上回る。
そんな経営者の不満が、会計士との関係を、“敵対”関係へと知らず知らずのうちに追いやっているのである。
だがこれは、経営者にとって不幸なことだ。特に直接、経理の現場に出ていく機会が限られる社長やCFOにとって、致命的である。
もちろん、社員を信頼するのは基本だが、過去からの「負の遺産」がある場合、いくら社長が口を酸っぱくして言っても、そう簡単に実態が明らかになることはない。事実を明かせば処分されたり、出世に響くと、実態を知る現場の管理職は考えるからだ。
ある大手製造業のトップは社長に就任して過去の問題を一掃しようと大リストラに着手した時、「責任は問わないから、過去の問題をすべて明らかにしろ」と厳命したという。にもかかわらず、数年たつまで問題が明らかにならなかったケースがいくつもあったという。「トップが会社の実像を正しく把握し続けることは、よほど覚悟を固めてやらないと難しい」とこのトップは言う。
そうした実態把握の力強い“味方”が、本来は会計士であるはずだ。その時は会社にとって厳しい会計処理でも、それを覆い隠して先送りすれば、必ずさらに大きなツケとなって将来の会社経営を揺るがす。粉飾決算はたいがい、ちょっとした問題の先送りから始まる。小さな嘘を隠すためにより大きな嘘をつくように、先送りした問題はどんどん大きくなる。それはオリンパスの巨額粉飾事件でも明らかになった。
社長やCFOが会社の本当の姿を把握し続けるには、会計士との対話を日ごろから重視することが必要だろう。一番の“味方”である会計士に実態を知ってもらい、経営者が気が付かない負の部分を知らせてもらう。
味方であるはずの会計士をいったん敵に回せば、後は嘘の上塗りの道へと突き進むしかなくなる。そうなれば、いつか会社は崩壊し、大リストラに多くの社員が泣くことになるのだ。多くの会社の経営者にとって、東芝問題は決して他人事ではない。
2016年1月15日






