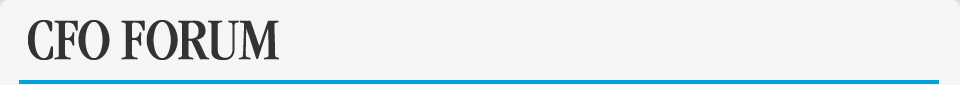
2015年12月15日
企業は誰のものか
森本 紀行
HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
なぜ、企業は誰のものかと問わねばならないのか。それは、何にでも所有者がいると考える思考の構造が前提にあるからで、現代資本主義経済体制の形成は、近代社会における私的所有権の確立を基礎にしているからである。
ゆえに、企業統治論は、企業を中核とした資本主義経済の将来へ向けた再検討ならば、現体制の思考構造を前提に、企業は誰のものかと問うのではなく、より根源的に、企業は誰のものかと問う背景の事情を検討することになろう。
さて、企業は誰のものかという問いは、企業統治論の通説を前提に、企業は株主のものであることの再確認を求めるものか、あるいは逆に、企業は本当に株主のものなのかという疑問を提示して、企業統治論の通説の再構成を求めるものなのか。
現実的には、この両極の間に、実際の企業統治のあり方を模索することになろう。要は、企業は株主のものであるとの見解を軸に、その周りに展開する批判的な検討を集積することで、企業統治論は形成されているはずなのである。
企業は、株主のものか、ステークホルダーのものか
企業が株主のものであるという主張は、株主が企業を所有していて、経営を専門家に委任しているという古典的な所有と経営の分離の延長にある議論である。
しかし、所有とは、完全に排他的で無制限な支配権のことだとしたら、株主が企業を所有しているとは到底いい得ない。株主の権利とは、株主総会における議決権(および、それに関連した提案権など)、配当を受け取る権利、清算時に残余財産の分配を受ける権利、この三つだけだからである。
しかも、議決権など、圧倒的な大株主でもなければ大きな意味はないし、配当についても、経営者の裁量に委ねられている以上、株主の権利は受動的なものにすぎない。残余財産分配権に至っては、このような権利が顕在化する状況においては、多くの場合、株主の利益が損なわれているときに違いないのである。
実は、企業には多くのステークホルダーがいるが、株主の地位はその誰よりも低いのである。取引先や従業員などは、契約によって明確に権利が守られている。金融関係の利害関係者についても、債権者の地位は厚く守られているが、株主の地位は債権者の地位に劣後している。
つまり、株主は、利益の分配においては最後であるにもかかわらず、損失の負担においては最初だということである。いわば、株主の権利に帰属する自己資本部分とは、ステークホルダーの利益を守るための万が一に備えた危険準備金にすぎない。所有権という強力な権利の意味からすれば、このような株主が企業を所有しているといえるはずはない。
かといって、企業はステークホルダーのものともいい切れない。株主の権利は、最も劣後するにしても、全く保護されないでいいとはいえないからである。むしろ逆で、最も劣後するがゆえにこそ、一定の保護が必要なのである。つまり、株主は、ステークホルダーに対して一種の保険を提供しているのだから、一定の対価を請求できるはずである。これが、株主を軸に据えた企業統治論の核心だ。
株主には、危険負担に見合った適正な利益が確保されなければならないということは、同時に、ステークホルダーについても、権利の保証の厚さの程度に応じた適正な利益が確保されなければならないということでもある。要は、企業統治論の目的は、株主とステークホルダーとの間の利益の公正公平な均衡に帰着するのである。
ところで、株主は最劣後の地位に甘んじている、つまり、一番大きな危険を負担しているのだから、一番大きな利益が結果的に帰属するのでなければ、不公平である。企業の経営者は、このことを正しく認識したうえで利益の均衡を図るべく経営しなければならない。ここに企業統治論は集約されるのである。
資本の論理における主役は、株主か、ステークホルダーか
原点において、株主が資本を拠出する。株主から経営を委任された経営者は、その資本を稼働させるために、販売先・仕入れ先などの取引先、従業員、債権者などのさまざまな利害関係者と契約を結ぶ。この契約相手方がステークホルダーである。
経営は、一方で、経営の継続のためにステークホルダーとの契約の履行は絶対要件だから、その利益を守るように株主に損失を負担させるのだが、他方で、経営の最終目的は、ステークホルダーとの関係の適正性を期すことで株主に対して資本利潤を還元することである。
結局、企業統治論では、企業の原点が株主による資本の拠出に置かれるわけで、経営者も、他のステークホルダーも、その資本の稼働のために動員される補助者であるわけだ。これが資本の論理である。企業統治とは、この資本の論理の貫徹である。
では、資本は主役であろうか。資本は稼働させてこそ利潤を生むわけだから、逆に、主役は資本を稼働させるステークホルダーではないのか。
確かに、危険負担と利益との適正な均衡に基づく資本利潤が還元できてさえいれば、企業経営は株主から独立したものとして運営できる、つまり企業はステークホルダーのものということも可能であり、あるいはより狭く、経営者と従業員のものということすら可能である。
要は、資本に対して適正な資本利潤の還元ができているかどうかにかかっているのだ。それができている限り、企業は経営者と従業員のものだといっても、株主は文句をいえない。資本利潤の還元を受けていないと感じる株主は、企業は経営者と従業員のものではないという。それが、企業は株主のものだという主張になる。
適正利潤か最大利潤か
さらに株主の主張を一歩進めれば、適正な資本利潤の還元ではなくて、資本利潤の最大化を要求することになる。資本の論理は、資本利潤の最大化を求めるのか、それとも、合理的な適正利潤で満足すべきなのか。
結局、企業は誰のものかという問いは、株主のものだという極と、ステークホルダーのものだという極との間に収まるのだが、そのことを別のいい方で表現すれば、資本利潤の最大化が企業の目的か、資本利潤の社会的適正化を目指すのが企業の目的かという二極の間に、企業統治論が収束するのと同じことである。
ここで決定的に重要なのは、時間軸の導入によって最大化という概念も大きく動くということだ。短期的な最大化は、長期的な最大化にはならないであろう。逆に、適正利潤は社会的に合理化されたものだろうから、反復継続性を期待でき、ゆえに短期的には利潤率が低いようにみえても、長期的には利潤の最大化につながり得る。
つまり、理論的には適正利潤と最大利潤が一致する経営の時間軸があり得て、そこでは株主の利益とステークホルダーの利益も公正公平に均衡する。いうまでもなく、「コーポレートガバナンス・コード」の求めている中長期的な企業価値の向上において、中長期的の意味は、その時間軸のことである。
さて、この理想の境地においては、もはや企業は誰のものかという問いは、意味を失っているであろう。そのとき所有を基礎とした資本主義経済体制は、超克されるのか。
2015年12月15日






