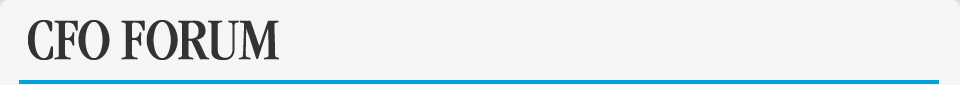
2016年2月15日

「両手効き」(Ambidextrous)の戦略が
個人も企業も救う
久原 正治
昭和女子大学現代ビジネス研究所長
-
①The Second Curve:
Thoughts on Reinventing SocietyCharles Handy
Random House Business, 2015 -
②オープン&クローズ戦略-日本企業再興の条件-
増補改訂版小川紘一
翔泳社 2015年12月
最近の欧米の経営学会では「両手効き」の戦略に関する研究がよくみられる。これは、一方で既存の知識を活用し、それを深めると同時に他方で新たな知識を得てイノベーションを探索するという、変動が激しい現代企業必須のダイナミックな戦略のことで、この活用と探索を同時に行わなければ企業は競争に敗退する。例えば前回の書評でも取り上げたインテル(次世代CPUへの果敢な投資)やアマゾン(本やDVDの実物ネット通販からクラウド配信へ)の戦略はまさにこれにあたり、たとえ自社の既存ビジネスと共食いになっても新たなビジネスに素早く投資し、環境変化にダイナミックに対応している。
この「両手効き」戦略が、個人にも企業にも必須になっていることを、最近内外で評判になっている2つの本を取り上げて考えてみたい。
①は、常に働くことの意味を問い続ける英国の経営思想家として著名なハンディが、シェル経営幹部、ロンドンビジネススクール教授、社会思想家とキャリアを転換してきた自身の人生を振り返りながら、個人も企業もそのピーク時に現在とは異なるキャリアや業務に投資することの必要を、「S字カーブ」の概念で分かりやすく説いている。
個人も企業も萌芽期から徐々に成長し、やがて急速に成長しピークに向かうが、ピークを過ぎるとやがて衰退に向かう。この成長曲線はS字カーブをとる。個人も組織も衰退の兆候に気付いて初めて、次の新たなキャリアや新業務に投資しようとするが、それでは手遅れになる。現在のキャリアや業務が絶頂のうちに同時に、次のカーブとなる新たなキャリアや革新的な業務への投資をスタートさせる(まさに「両手効き」である)必要を著者は述べている。
著者は、世界の企業組織は株主中心から知識を生む従業員中心に、身動きのつかない巨大企業から俊敏な小企業組織に変革していき、その中で知識労働者として働く人々は良い人生を送らねばならないことを80年から90年代にかけ次々に出版した経営啓蒙書で述べてきた。本書は著者が80歳を過ぎて、これまでの自らのキャリアと現代資本主義の将来に関する思考を振り返り、激しい経済環境の変化の中で右往左往する我々に資本主義の将来とその中で働く人々の生き方を問いかける良書となっている。著者の英語は含蓄があり、具体例が多いこともあって読みやすいので、多少時間のある方は一度手に取って読むことをお勧めする。
②の著者は、富士通総研から東大ものづくり経営研究センター特任研究員などを経て、日本の製造業の産官学協働を通じた再生の具体的な提言を続けている。本書は、2014年の前書を最近のIoTの動きなども入れ昨年末増補改訂したものだが、専門家の間で定評があるだけでなく、日本の製造業の将来に興味を持つ一般の読者にもわかりやすい良書だ。
著者は日本の製造業が、自社のコア領域(クローズド)と他社に重ねる領域(オープン)を同時に開発しながら(これも「両手効き」の戦略である)、オープンにつながる境界に知的財産権を集中することで、グローバルな競争に勝ち残ることを示している。
日本のエレクトロニクス産業は、モジュール型のオープン化が急激に進んだ中で、高い技術イノベーション力を持ちながらそれぞれのコア領域を守る知的財産戦略に不備があったために、自らのクローズなコア領域まで一気に新興国に伝播することで競争力を失ったとする。これらのコア領域はいずれも、技術イノベーションだけではなく、ビジネスの仕組みづくりとこれを支える知的財産権や契約の組合せによって守られており、コアとなる領域の外では、国際標準化などを活用するオープン化が徹底されている。このオープンとクローズの全体をエコシステムとして、産業構造を自社優位に構築した企業だけが競争に勝利する。
この20年間に急速に競争力を失った日本の製造業が、半導体やエレクトロニクスのように、実は高い技術イノベーション力を持ちながら、それをグローバル化が進んだエコシステムの中で生かすことができなかったことに対する強い危機感から、著者は豊富で具体的な企業事例により主張を展開している。
2016年2月15日




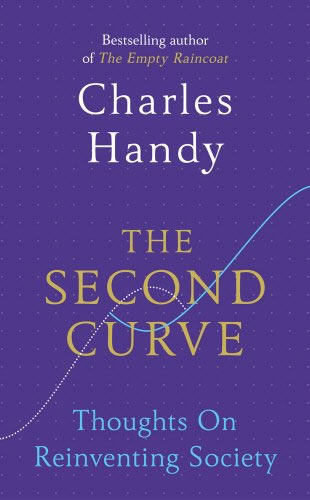

![【特集】ファイナンス部門のトランスフォーメーションはなぜ必要か?[後編] 【特集】ファイナンス部門のトランスフォーメーションはなぜ必要か?[後編]](https://forum.cfo.jp/wp-content/uploads/2022/11/kikaku_ictach.jpg)

